
こんにちは、てつやまです。
今日紹介する1冊はこちら
『頭がいい人が話す前に考えていること』安達裕哉

本書は、「ちゃんと考える」とはどういうことかを、考えさせてくれる本です。
この本は、「頭のいい人が考えていることを要約したもの」ではなく、
「頭のいい人になるためのプログラム」を体験するものです。
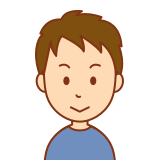
なんでこの本を読んだの?

書店の売り場で、一番目立っていました。
話題の本らしいので、読んでみたくなりました。
本の内容で大事な3つのポイント
①知識ではなく「知性」を身につける
②相手の立場に立って考える習慣をつける
③感情をコントロールして冷静さを保つ
一つずつ解説していきます!
①知識ではなく「知性」を身につける
「知識」は情報、「知性」はそれを活かす実践力
本書を読んで最初に気づいたのは、「知識」と「知性」の違いです。
知識とは単なる情報の集積に過ぎません。
一方、知性とは、その知識を実際の場面で活用できる力のことです。
例えば、英単語をたくさん覚えていても、実際の会話で使えなければ意味がありません。
同様に、ビジネス書をたくさん読んでいても、その知識を実際のビジネスシーンで活かせなければ
「知識」のままで「知性」とは呼べないのです。
「何のためにこれをするのか」を明確にするマインド
著者は、知性を身につけるためには、実践が必要だと強調しています。
知識はインプットするだけでは不十分で、それを自分の血肉にするためには何度も実践し、
失敗を繰り返す必要があるのです。
私自身もこれまで、多くの本を読み、セミナーに参加し、知識を得てきましたが、
それを実際に使うことは意外と難しいと感じていました。
なぜなら、知識を得ることと、それを実際に使いこなすことの間には大きな隔たりがあるからです。
本書では、野球やゴルフのフォームを例に挙げ、「基本のフォーム」の重要性を説いています。
しかし、そのフォームを身につける前段階の「マインド」がなければ、
「何のためにやっているのか分からず、モチベーションが保てない」などの
弊害が生じると指摘しています。
私自身、プレゼンテーションのスキルを向上させたいと思い、様々な技術書を読みました。
しかし、「なぜプレゼンが必要なのか」「何を伝えたいのか」というマインドが明確でなかったため、テクニックだけを学んでも上達しませんでした。
正しいフォームで繰り返す
「知識」を「知性」に変えるためには、まず「マインド」を整え、
その上で「フォーム」を正しく身につけることが大切なのです。
そして、それを何度も繰り返し実践することで初めて「知性」と呼べるものになるのです。
私たちは往々にして「知っている」ことと「できる」ことを混同してしまいがちです。
しかし、本当の頭の良さは、知識の量ではなく、その知識をどう活かすかにかかっているのです。
②相手の立場に立って考える習慣をつける
「頭のよさ」は周りが決めるもの!
本書で特に印象的だったのは、「頭のよさは他人が決める」という言葉です。
この言葉は、自分が頭がいいと思っても、周りがそう思わなければ意味がないということを示しています。
では、周りから「頭がいい人」と認められるにはどうすればよいのでしょうか。
著者によれば、それは「相手の立場に立って考える」ことだと言います。
具体的には、話す前に「相手が聞きたい結論」を意識することが重要です。
私たちは、ついつい自分が言いたいことから話し始めてしまいがちです。
しかし、相手が求めているのは、「そういうことじゃないんだよなあ」ということが多いのではないでしょうか。
例えば、上司から「昨日の契約はどうだった?」と聞かれた場合、
相手が本当に知りたいのは「契約が取れたかどうか」です。
また、「なんで遅刻したの?」と聞かれた場合は、
「遅刻の理由と今後の対応策」を知りたいのです。
これまで私は、質問された時に思いついたことをそのまま話してしまうことが多く、
「結局どういうこと?」と言われることがありました。
本書を読んで、それは「相手が聞きたい結論」から話していなかったからだと気づきました。
「本当に相手のため?」を立ち止まって考える
また、著者は「簡単にアドバイスするな」とも述べています。
私たちは知識を持っていると、つい相手のためと思ってアドバイスしたくなります。
しかし、そのアドバイスは本当に相手のためになるのでしょうか。
単に自分が知識を披露したいだけではないでしょうか。
「本当に相手のためになるか?」と一度立ち止まる習慣をつけることで、
より効果的なコミュニケーションができるようになります。
相手に受け入れられるアドバイスとは、相手の立場を理解した上で行うものなのです。
私自身、上司や同僚にアドバイスをする際に、つい自分の経験や知識を一方的に伝えてしまうことがありました。
しかし、相手の状況や感情を考慮せずに行うアドバイスは、往々にして受け入れられないことが多かったのです。
相手の立場に立つのは「話す前だけ」でOK
「相手の立場になって考える」というのは、常にそうしなければならないわけではありません。
著者が言うように、「話す前だけでいい」のです。
普段は自分の感覚を大切にしながら、好きなことを考え、
話す前だけ相手の立場に立てば十分なのです。
③感情をコントロールして冷静さを保つ
「とにかく反応しない」が基本
本書の中で、私が最も実践したいと思ったのは「感情のコントロール」です。
著者は「感情的になったら『とにかく反応しない』ことを心がける」と述べています。
北野武監督の映画『アウトレイジ』を例に挙げ、
「殺されるのは感情的になった人間」だと説明しています。
これは比喩的な表現ですが、感情的になると人は愚かな行動をとりやすくなる
という事実を表しています。
冷静であれば言わないことでも、感情的になるとつい口走ってしまうことがあります。
しかし、一度言葉にしたものは取り消すことができません。
そのため、感情的になった時は「とにかく反応しない」ことが大切なのです。
怒りをコントロールする「6秒ルール」
本書では「アンガーマネジメント」という心理トレーニングを紹介しています。
そこでは、怒りが生まれてから理性が働くまでにかかる時間は「6秒」
だと言われています。
この「6秒ルール」を意識し、感情的になった時は、
少なくとも6秒間は何も言わないようにすることで、冷静さを取り戻すことができます。
私自身も、感情的になって後悔した経験があります。
例えば、上司からの厳しい指摘に対して感情的に反論し、
結果的に関係を悪化させてしまったことがありました。
もし、その時に「6秒ルール」を実践していれば、冷静に対応できたかもしれません。
感情的になると、自分の感情を相手にぶつけることで、一時的にスッキリした気分になりますが、
長期的には信頼関係を損なう結果になります。
「とにかく反応しない」ことで、そのような事態を防ぐことができるのです。
冷静になるための時間を稼ぐ!
もちろん、人間は感情の生き物なので、感情をゼロにすることはできません。
大切なのは、感情的になっていると気づいた時に、冷静さを取り戻す時間を確保することです。
そのためのテクニックとして「6秒ルール」は非常に有効だと思います。
私は今後、感情的になりそうな場面で「6秒ルール」を実践し、冷静な判断ができるよう心がけたいと思います。
まとめ
繰り返しとなりますが、本書のポイント
①知識ではなく「知性」を身につける
②相手の立場に立って考える習慣をつける
③感情をコントロールして冷静さを保つ
著者は最後に
「頭のいい人になることより、頭のいい人であり続けることのほうが難しい」と述べています。
これは非常に重要なポイントだと思いました。
知識を得て「頭のいい人」になることは、それほど難しくありません。
しかし、その知識を実際の場面で活用し、常に「頭のいい人」として行動し続けることは非常に難しいのです。
それは、「知識」と「知性」の違いと同じです。
知識を得て、それを血肉とし、繰り返し実践した先に「知性」があります。
そして、その実践こそが大事だというのが著者のメッセージなのです。
私もこれまで多くの自己啓発書を読み、一時的には「頭がよくなった気分」になりました。
しかし、その知識を実際の生活で活用し続けることができず、結局は元の状態に戻ってしまうことがありました。
本書を読んで、「知識」を「知性」に変えるためには継続的な実践が必要だと改めて認識しました。
そして、「相手の立場に立って考える」「感情をコントロールする」という具体的な方法を知ることができました。
これからは、本書で学んだことを日常生活で実践し、真の意味で「頭のいい人」になれるよう努力していきたいと思います。
「頭がいい」というのは、決して生まれつきの能力ではなく、適切な思考法と継続的な実践によって誰でも身につけられるもの。
そして、その思考法の核心は
「知識を知性に変える」
「相手の立場に立って考える」
「感情をコントロールする」
という3つのポイントに集約されると言えるでしょう。
この本は
・「ちゃんと考えろ」と怒られる人
・「ちゃんと考えろ」の「ちゃんと」とは、どうすればいいのか知りたい人
・コミュニケーションが苦手な人
におすすめな一冊です!
この本が気になった方は、是非下記リンクからご確認ください!
↓



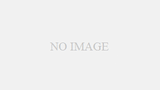
コメント