
こんにちは、てつやまです。
今日紹介する1冊はこちら
『話すだけで書ける究極の文章法 人工知能が助けてくれる!』野口悠紀雄

本書は、音声入力の進化がもたらす、新たな執筆スタイルに注目した一冊。
著者・野口悠紀雄氏が、スマートフォンの音声入力機能を活用して完成させた本。
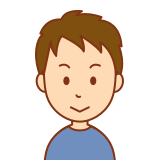
なんでこの本を読んだの?

「話すだけで書ける」と言うワードに惹かれ、音声入力による文章術を学びたいと考え、読んでみました。
本の内容で大事な3つのポイント
①「書き始めの壁」を音声入力が突破してくれる
②書く価値は「何を書くか」で決まる時代に突入!
③「語れる分野」が、文章に説得力を宿らせる
一つずつ解説していきます!
①「書き始めの壁」を音声入力が突破してくれる
音声入力が執筆を変えたリアル
文章を書く際、一番つまずきやすいのが“最初の書き出し”。
音声入力はこの壁を劇的に低くしてくれる手段です。
話すことで自然に思考が流れ始め、「考える」と「書く」という、マルチタスクの負担を減らしてくれます。
最初の一歩がラクになることで、執筆への意欲も続きやすくなります。
本書が、スマートフォンの音声入力を使って書かれたという点、非常にユニークだと思いました。
著者の野口悠紀雄氏は、実際にこの手法を使って1冊を書き上げており、
「音声入力によって文章のスタートが劇的にラクになる」
という主張には実体験が伴ってるな、と感じました。
音声入力は「長文」で進化を発揮する!
私は「話すだけで書ける」という言葉に強く惹かれ、この読書感想 ブログのためになる、何かヒントが得られるのではと思って、本書を手に取りました。
結果は予想以上でした!!
これまでは「文章を書くにはじっくり机に向かい、キーボードを前にして悩まなければならない」と思っていました。
しかし、本書を読んだ今は「話しながら考えること」の方が、自分には向いていると感じています。
特に印象的だったのは
「長文になればなるほど、この『楽さ』の落差は、大きくなっていくのです」
という一節です。
長文を書く際の苦しさは、私も何度も経験しています。
途中まで書いて、違うと感じて消して、また書き直して…
しかし音声入力なら、話すうちに、自然に思考が流れ、ページをまたぐようなボリュームも苦になりませんでした。
音声入力が長文執筆において新しい可能性を開いてくれる
――まさに執筆スタイルを根底から変える、革命的な方法です。
②書く価値は「何を書くか」で決まる時代に突入!
「テーマの独自性」で“違い”を作る!
スマホ一つで文章が書けるようになった今こそ、問われるのはアイディアの中身。
「みんなと同じ」に安心する空気ももちろんありますが、文章では“違うこと”に価値が生まれます。
テーマの独自性が、読み手の心をつかむ一番の要素です。
本書では「文章の価値は、どのようなテーマを見いだすかで、ほとんど決まります」と明言されています。
特に音声入力のように技術的な壁が取り払われた今だからこそ、「何を書くか」にこそ注目すべきだと強調されています。
違い=武器!テーマ設定の重要性
私が「どのようなテーマを見出すかが大事」という言葉に、心から納得した理由は、自分の中に「人と違う視点」を書きたい欲求があったからです。
しかし、これまでその違いは「協調性の欠如」と見なされがちで、あえて表に出すことを躊躇していた節があります。
だが、この本が「違う価値観を持つことは、文章においてはプラスに働くのかも」と背中を押してくれました。
実際、音声入力によって文章を書くハードルが下がった分、誰もが文章を書くようになった今では、表現そのものよりも「中身」が差を生む時代です。
そこで本書は「何を書くか」「どんなテーマを選ぶか」を深く掘り下げるよう導いてくれます。
テーマ設定こそが、読む人の心を動かす鍵になる。
これはブロガーにとっても、非常に実践的な指針だと感じました。
③「語れる分野」が、文章に説得力を宿らせる
「語れる」が、説得力のある文章のカギ!
「自分が1時間話せる内容」は、経験や興味が深く根づいている証。
それこそが、書くべきテーマだと本書では解説しています。
浅い理解のまま書こうとしても決して 伝わりません。
集中して、考え抜いた先に、アイディアにも説得力が生まれるもの。
だから、「何なら長く話せるか」を知ることが、良質な文章の入り口となります。
このポイントは、本書の中でも最も現実的かつ自己分析につながる部分だと感じました。
著者は「1分しか話せないテーマではエッセイを書くことができない」と述べていますが、その理由は単純です。
そこに自分自身の言葉や経験がないからです。
私自身、あるテーマではスラスラ話せるのに、別のテーマでは頭がフリーズすることがあります。
そんな体験を経て、培われてきた「語れる分野」が、そのまま文章力の源泉になるのです。
知識を試して、自分らしく磨くことで、知恵となる!
さらに「知識は知恵になっていく」という一節には、著者の深い理念を感じました。
ただ情報を得るだけではなく、それを話してみて、自分に合うスタイルを見つけ、繰り返して使いこなす
――そのプロセスを通して、文章は“読まれるもの”へと昇華する。
単なる知識を、自分のスタイルで「知恵」にアップグレードする。
だからこそ、「これは!?」と目を引く文章となるのでしょう。
「ひらめき」の前には、「問題に集中する時間」がある!
また、アイディアを出すには「問題に集中する時間が必要」とする視点も、本書の重要な要素です。
リラックスした時に、ふと浮かぶアイディアは、その問題に真剣に取り組んだ時間があったからこそ生まれる。
これは、深く考えた者だけが得られる“ひらめき”であり、「語れる分野」を持つ人にしか書けない文章を生む土壌なのです。
まとめ
繰り返しとなりますが、本書のポイント
①「書き始めの壁」を音声入力が突破してくれる
②書く価値は「何を書くか」で決まる時代に突入!
③「語れる分野」が、文章に説得力を宿らせる
この本を通じて私が得たものは、音声入力という技術以上に、
「書くとは何か」という本質的な問いへのヒントでした。
「書き始めの壁」を壊すきっかけとしての音声入力。
誰もが文章を書ける時代だからこそ必要になる「テーマの独自性」。
そして、自分が「語れる分野」を見つけることで生まれる説得力
――それらが三位一体となって、文章が読み手に届く力となります。
文章術の表面だけでなく、思考法や自己認識の深度を問う本書は、書き手としての自分をもう一度見つめ直す貴重な機会となりました。
「話すだけで書ける」
――このシンプルで強力な提案に触れた今、私はこれからも、自分の中にある“話せる何か”と向き合いながら、言葉を紡いでいきたいと思います。
この本は
・考えすぎて書き出せない人
・「自分にしか語れないことって何だろう?」って思ってる人
・話すことなら好きだけど文章は苦手な人
におすすめな一冊です!
この本が気になった方は、是非下記リンクからご確認ください!
↓



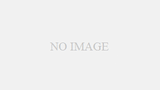
コメント