
こんにちは、てつやまです。
今日紹介する1冊はこちら
『読書は鼻歌くらいでちょうどいい』大島梢絵

本書は、読書初心者に向けた「本との向き合い方」を綴ったエッセイ。
読書が苦手な人ほど、読書のハードルは高いもの。
そんなハードルを、できるだけ低くしてくれる本。
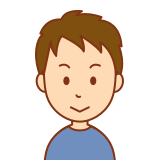
なんでこの本を読んだの?

読書が趣味だから。
他の人の「本との距離間・付き合い方」に興味があり読んでみたくなりました。
本の内容で大事な3つのポイント
① 本との距離感は自分のペースで
② 印をつけるのは「忘れたくない気持ち」のため
③ 読書はデジタルデトックスにもなる
一つずつ解説していきます!
① 本との距離感は自分のペースで
「べき論」でプレッシャー!?読書本来の楽しさが見失われている…
読書に対する「べき論」が、私たちを苦しめているのでは?
著者は、そんな疑問に対して、警鐘を鳴らしています。
「1日30分は読まなくては」
「年間100冊達成しなくては」
というノルマは、本来自由であるはずの読書体験を、窮屈なものにしてしまいます。
著者は「本を読むという行為には、その時の自分の状態や気分が大きく関わるので、
『いつ読むか』というタイミングこそ重要」だと指摘します。
確かに、同じ本でも読むタイミングによって、その印象や得るものは大きく異なります。
学生時代に読んだファンタジー小説と、社会人になってから読み返した同じ小説では、
全く違った感想を持つことがあります。
本と出会うタイミングが大事!
また、人生の節目で出会う本には、時に運命を変える力があります。
就職活動で悩んでいるときに読んだ自己啓発書。
恋愛に悩んでいるときに手に取った小説。
キャリアの転機で出会ったビジネス書。
それらの本が心に染み入るのは、まさにそのタイミングだからこそ。
逆に、いくら名著と言われる本でも、自分の状態とマッチしなければ、心に響かないことも…
「選書サービス」とは、絶妙なタイミングを見極める職人技
他人に本を薦める時も同じです。
「オススメな本教えて!」と言われたとき、
著者は「あなたが今読んでる本教えて!」と脳内変換してやり過ごすと言います。
相手の現在地を知らずに、おすすめの本を紹介することの難しさを、
著者は経験から学んでいるのです。
だからこそ、人に本を選ぶ「選書サービス」は、長年の経験値の賜物。
ただ本の内容を知っているだけでなく、
「この人にはこのタイミングでこの本が響くだろう」
という繊細な感覚が必要なのです。
本との距離感は千差万別。
自分のペースで、自分の気分で、自分の状態に合わせて本と付き合う。
そんな肩の力の抜けた読書のあり方を、著者は提案しています。
② 印をつけるのは「忘れたくない気持ち」のため
本に線を引くのは、「忘れたくない気持ち」を残すため
本に線を引いたり、付箋を貼ったりする行為。これも読書における一つの習慣です。
しかし著者は、その「目的」について再考を促します。
本の「内容」を忘れないようにということではなく、
「忘れたくないと感じた気持ち」を忘れないための印である―
著者のこの言葉に、私は深く共感を覚えました。
本に印を付ける人の中には
「本を読んだら、一つでも多くの気づきを得たい」
と感じながら読書をしている人も多いのではないでしょうか。
特にビジネス書やハウツー本を読む際、「これは使える!」「これは覚えておきたい!」と思う箇所に線を引いたり、マーカーで色を付けたりすることがあります。
その際、覚えていたいと思うのは単なる「情報」についてのこと。
読書の楽しみは「自分との対話」にあり!
しかし、そんな風に読書をしていると、読書を楽しむ視点が薄れていってしまうと、
著者は指摘します。
インターネットで情報を素早く手に入れることができる現代、ただ情報を得るだけではなく、
読書自体の楽しみの部分に目を向けていきたいと感じました。
では、なぜ印を付けるのか。
著者は「忘れたくないと感じた気持ち」を忘れないためと述べています。
私も、特にビジネス書には多くの印をつけます。
そして読み終わってしばらくたち、ふと読み返した際、
「ああ、こんなところに印がつけられている」と懐かしい気持ちになります。
人間は成長し、変わりゆくもの。
過去印をつけていても、今の自分にはそれほど響かないこともあります。
それは成長している証だととらえ、それらを糧に人生を楽しんでいきたいと思います。
また、印をつけることで、本との対話が生まれるという側面もあります。
「この部分に共感した」「ここは疑問に思った」という自分の反応を記録することで、
単なる受動的な読書から、能動的な読書体験へと変わります。
本の内容と自分の考えが交錯する場所に、読書の醍醐味があるのかもしれません。
アウトプット優先の落とし穴
読書の意義について考えるとき、著者は
「インプットよりアウトプット優先の思考回路になってしまっては、大切なものを見逃してしまいそう」と警告します。
私自身、ブログを書き始めた当初、
「ブログに載せるための読書」という側面が強くなっていると感じることがありました。
SNSで共有するために読む。
読書会で話すために読む。
仕事で使うために読む。
そんな目的主導の読書が増えていくと、本来の読書の楽しさが失われていきます。
楽しいから読んでいた本。
面白いから続けていた読書。
しかし、アウトプット優先の思考では、そんな楽しみや喜び、そして「何かを得ている」という実感もなく、ただただ作業となってしまいます。
読了本数を増やすことが目的化し、内容を十分に味わう余裕もなくなってしまうのです。
たとえ、読書がアウトプットを念頭に置いているとしても、
読んでいる最中くらいは、本に向き合い、そして自分自身とも向き合う時間でいたいと思います。
それこそが、デジタル社会において希少となりつつある
「深い思考」の時間ではないでしょうか。
著者の言葉は、読書そのものの価値を再確認させてくれます。
読書は単なる情報収集ではなく、自分の内面と対話する貴重な機会なのです。
③ 読書はデジタルデトックスにもなる
「デジタルデトックスしたい」と「読書に向き合いたい」はリンクする
現代社会において、私たちは絶え間なく、情報の洪水にさらされています。
スマホを手に取れば、SNSの通知、メール、ニュース速報が次々と押し寄せてきます。
著者は「デジタルデトックスをしたい」と思い立ったタイミングが、
「しっかり読書に取り組みたい」と考えていた時期と重なったと述べています。
これは単なる偶然ではなく、現代人が抱える共通の課題を示しているように思えます。
私自身、暇なときはついついYouTube など 動画をみて過ごしています。
ついついみていると、平気で1時間くらい経ってしまい、
「もうこんな時間か…」と、倦怠感に襲われたりします。
何かの待ち時間、電車の中、寝る前のひととき。
スマホをスクロールする指が止まらなくなる経験は、多くの人が共感できるのではないでしょうか。
読書が心のデトックスになる!
そんな、インターネット社会から隔離する時間というのは、今後ますます大事になるはずです。
情報過多による疲労、SNS疲れ、常に「繋がっている」ことへのプレッシャー。
これらから解放される時間は、心の健康を保つために必要不可欠なものとなります。
そんなデトックスのお供に本を選ぶのは、インドア派の私に向いていると感じました。
読書は、デジタル機器から離れつつも、家の中で静かに楽しめる贅沢な時間です。
紙の本を手に取り、ページをめくる感触、印刷されたインクの香り、文字を追う目の動き。
これらのアナログな体験は、デジタルでは得られない満足感をもたらします。
スマホやSNSも、お酒やゲームと同じように、適度に楽しめば、薬となります。
著者の言葉を借りれば、「ほどほどで楽しんでいきたい」。
読書は、そんなデジタルとの適切な距離感を取り戻す助けになってくれるのです。
鼻歌のように気軽に、でも心地よく
『読書は鼻歌くらいでちょうどいい』というタイトルには、著者の読書哲学が凝縮されています。
鼻歌は、特別な場所や時間を必要とせず、ふと口ずさむもの。
重大な目的があるわけでもなく、誰かに聴かせるためでもなく、
ただ自分が心地よいと感じるから口ずさむ。
そんな自然な行為として読書を捉え直すことで、私たちは「読書しなければ」という義務感から解放され、心地よい 読書ができるはずです。
通勤電車の中で少し読む、寝る前にほんの数ページ読む、休日の午後にカフェで読む。
そんな日常の隙間に、自分のペースで本を楽しむ。
それこそが「鼻歌のような読書」なのではないでしょうか。
読書は、歌うのと同じ。周りを気にせず自分のペースで楽しむのが大事!
また、著者は
「読書の楽しさは、歌を歌うときのように自分のペースで進められること」
と述べています。
確かに、歌うときも誰かのペースや評価を気にしていては、楽しく歌えません。
同じように読書も、他者の視線や評価から解放された、自分だけの時間として楽しむことが大切なのです。
また、鼻歌は心の状態を表すものでもあります。
楽しいとき、集中しているとき、リラックスしているとき。
そんな自分の気分や心の動きに合わせて、本を選び、読むペースを決める。
そんな自由な読書のあり方を、著者は提案しています。
まとめ
繰り返しとなりますが、本書のポイント
① 本との距離感は自分のペースで
② 印をつけるのは「忘れたくない気持ち」のため
③ 読書はデジタルデトックスにもなる
『読書は鼻歌くらいでちょうどいい』を読み終えて、私は長年抱えていた読書に対する、
「〈趣味が読書〉の重圧」という重荷を、下ろすことができた気がしました。
「正しい読書法」なんて存在しません。
あるのは、自分にとって心地よい、自分らしい読書との付き合い方だけ。
読書は決して義務ではありません。
それは自分自身と向き合い、時に逃避し、時に成長するための、かけがえのない時間です。
鼻歌のように気軽に、でも心から楽しめる読書体験を、これからも大切にしていきたいと思います。
この本は
・読書になれていない人
・読書を習慣化したい人
・デジタルデトックスしたい人
におすすめな一冊です!
この本が気になった方は、是非下記リンクからご確認ください!
↓



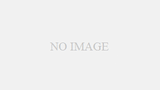
コメント