
こんにちは、てつやまです。
このたび、青崎有吾さんの頭脳バトル小説
『地雷グリコ』を読みました。
《作品情報》
・書名 地雷グリコ
・著者 青崎有吾
・出版社 KADOKAWA
・頁数 348
1.この本のここが凄い!
日常の中の【非日常】。
相手の隙を伺い、一発逆転へいざなう爽快感。
頭脳戦バトルの緊張感を、「人が死なないミステリ」として味わえる作品。
なぜこの本を読んだのか
青崎有吾さんの『体育館の殺人』を読み、その論理の構築からくるミステリに魅了されました。
同じ著者による「心理戦バトルもの」と聞き、
かなりの期待をしながら、読み始めました。
2.かんたんあらすじ
平穏な日常を夢見る射守矢真兎。
だが、彼女の非凡な勝負強さが、彼女を波乱の舞台へと導く。
親友・鉱田の頼みで参加したのは、学園祭の屋上使用権を懸けた伝説の争奪戦《愚煙試合》。
その決勝戦で執り行われたのは、誰もが知る「あのゲーム」で…
少年漫画のように次々と現れる強敵たち。
そんな猛者たちとのゲームの裏をかき、絶望的状況をひっくり返せ!!
緊張感と驚きが交錯する、青春頭脳バトルストーリー。
心に響いたフレーズ
《愚煙試合》はそのために作られたんじゃないかとオレはにらんでる。勝負に強いやつを効率よく見つけ出すためにな
頬白高校生徒会長・佐分利のセリフ。
愚煙試合とは、文化祭で、屋上の使用権をゲームで奪い合う頬白高校の伝統。
それがなぜ生まれたのか、を会長が考察しているセリフ。
他校と戦う「ずる賢い」奴らを集めるための催し…
《愚煙試合》のネーミングも、「馬鹿と煙は高いところが好き」をうまく言いあらわした言葉だと感じました。
この場合の馬鹿は、知能が不足しているというよりも、
「常識はずれの異才」
を意味しているのではないかと思います。
そして、この本のタイトル『地雷グリコ』というゲームを、
その愚煙試合決勝で披露し、しかも本の構成上冒頭に持ってきている点、
本に最初から入り込める、素晴らしい仕掛けでした。
《愚煙試合》決勝だけにすることで、それまでの熱戦を、
後日談としてまとめて続編に回すことも可能。続編への期待でわくわくします。
「六千万円をかけた勝負でしょう」かぶせるように、塗辺くんは言った。「僕も、射守矢さんも、雨季田さんも、マジですよ」
最終戦《四部屋ポーカー》の三回戦目。
ライバルキャラの雨季田の策略で、騒然となる場を制した、審判・塗辺のセリフ。
その後、射守矢の
「いまの《チェンジタイム》中、何かルール違反はあった?」
「ありませんでした」
という対話も、読み返して見事だと感じました。
ゲームのルールの裏をかこうとするプレイヤーたちの行動。
そのルールに違反するかを、冷静に、ジャッチしている姿に職人技をみました。
このセリフのインパクトは、作中一番かもしれません。
そんな彼女たちを普通の世界に引きずりおろして、角を削って、心を満たして、日常に留めておく。そして本当に困ったときだけ力を借りて、助けてもらう。それが私の戦略なのかもしれなかった。
主人公・鉱田のモノローグ。
生存戦略の話から、自分の戦略を言い表した場面。
本書のテーマの一つとして、たびたび【生存戦略】の話題はでていましたが、
鉱田が語るのは、このときが初めてだったと思います。
非日常を生きる可能性が高い者を、日常につなぎとめる。
それは、名探偵における助手の役割でもあるんだな、と妙に納得しました。
どちらが優れているという話ではなく、戦略が異なるというだけの話。
名探偵に重きをおきがちなミステリの見方を、良い意味でほぐしてくれた場面です。
3.まとめ
読んだことで得られたポイント
何度も読み返したくなる作品です。
続編を示唆している終わり方で、シリーズ化に期待が持てます。
個人的には、審判役の塗辺(ぬりべ)の有能さが、
ゲームのハラハラ度を保証していたと感じました。
高校一年生男子で、ラクロス部という脇を固める名バイプレイヤーです。
また、ジャンプ漫画のような「強さのインフレ」のおかげで、飽きることなく読むことができました。
「この人めちゃくちゃ強そう!」というキャラが登場しては、箸休めをはさみながら…
と展開されていくので、一気に読むのに適していると感じました。
射守矢というキャラクターは、人生経験からくる洞察力ではなく、
論理と思考の行きつく先での優れた洞察力という点が、
青崎有吾さんの登場人物らしいと感じました。
「若者のほうが頭が柔らかい」という言葉はよく聞きますが、さらに人生経験も加われば、
恐ろしいほど魅力的な人物になるのではないかと感じました。
この本は
・頭脳バトル好きな人
・最後に大逆転する話が好きな人
・人が死なないミステリが好きな人
におすすめな作品です!
この本が気になった方は、是非下記リンクからご確認ください!
↓

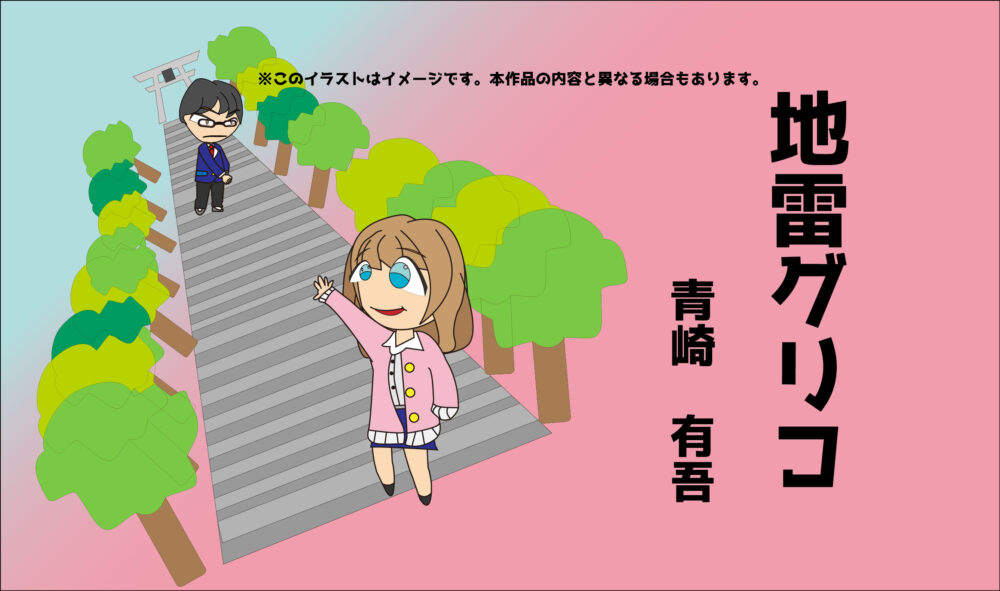

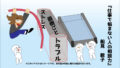

コメント