
こんにちは、てつやまです。
このたび、EDAさんの異世界料理小説
『異世界料理道④~⑤』を読みました。
《作品情報》
・書名 異世界料理道④~⑤
・著者 EDA
・出版社 株式会社ホビージャパン
・頁数 331/333
1.この本のここが凄い!
「異世界×料理」というのは、珍しいものではありません。
しかし、本作品が他の料理ファンタジー小説と違うのは、「チート」が全くないこと!
一つ一つ、異世界の食材と、見知った現代の食材を照らし合わせ、試行錯誤で料理していく。
そうして、料理を通じて、人と人の縁を紡ぐところが、ハートフル!
なぜこの本を読んだのか
他作品よりも、リアルに描かれた異世界料理小説だったから読み進めました。
没入しながら読むことができ、主人公とともに成長できる作品。
2.かんたんあらすじ
異世界に迷い込んだ少年が、料理の腕で、森辺の民と呼ばれる狩人の部族たちとの縁を結んでいく話。
4~5巻は、異世界の町、料理道開業編。
心に響いたフレーズ
「あんたには不味くても、俺には死ぬほど美味かった。そんなものは人それぞれだろ。」
第4巻。南の民ジャッカル人、大工の副棟梁・アルダスのセリフ。
森辺の民、最長老のジバ=ルウも言っていたが、食の好みは千差万別。
美味いも不味いも、自分次第。
だから
「これは不味いはずだ」
「美味く感じないなんておかしい」
などは、言うだけ野暮。
そして、年長者である棟梁のバランにもはっきりもの申すのも、
直情的な南の民の気性をあらわしている、と感じました。
そして、飴と鞭。
バランのおやっさんが貶し、アルダスが褒める。
一方的に褒められるのは、しらける。
かといって、貶されるだけでは、話が重すぎて読みたくなくなる。
食の好みは人それぞれ。
人の行動も、ある側面では貶されることも、別の側面からなら褒められる。
「人生とはこんなもの」
「楽あれば苦あり」
というメッセージを感じました。
「同じ西の民でありながら、俺はどうしても森辺の民を同胞だと思うことができなかった。今でもおっかない男衆の姿なんて見ると足がすくんじまうんだが……それでも、あんたがたみたいな森辺の民もいるんだなってことを知ることができたのは、本当に良かったと思ってる」
第4巻。野菜売りのドーラの親父さんのセリフ。
一般的な西の民である親父さんの、正直な心情を吐露している場面。
アスタを通じて、森辺の民たちの気質を感じ取っていく親父さん。
長年、森辺の民たちに抱いていた畏怖。
いくら自分の目で見て、気質を知ろうとも、長年の積み重ねが0になるわけではない。
その感情の機微を言い表している、とても重要な場面。
この本が気になった方は、是非下記リンクからご確認ください!
↓
外見はなよやかでありながら、アスタの内には狩人にも劣らぬ勇猛さと誇りが備わっているようだった。
第5巻。「箸休め ルウの分家のかまど番」より。
シーラ=ルウのモノローグ。
森辺の民としては、身体が弱かったシーラ=ルウ。
そんな彼女のことを、疎ましく思う眷属はいなかった。
しかし、他者から責められないかわりに、自らが無力感を募らせることに…
そんな彼女が、とりわけ好んでいたのが「かまど番」の仕事だった。
料理道具くらいなら運ぶことも可能なシーラ=ルウ。
そして、かまどの間ならば家族しかいないので、他の人と比べてしまうこともない。
そんなかまど番を好むシーラ=ルウと、異国人であるアスタが出会う。
異国人でありながら、自らの料理の力で、居場所を見出そうとするアスタに、
シーラ=ルウ自らの希望
「森辺で誇り高く生きていく」
を重ねていたのかもしれない。
そんなシーラ=ルウからみた、アスタを言い表している場面。
本編は、アスタの視点で描かれています。
そのため、外伝的なこの章は、別視点からみたアスタ評でとても新鮮で面白い、と感じました。
この本が気になった方は、是非下記リンクからご確認ください!
↓
3.まとめ
読んだことで得られたポイント
シリーズ4、5巻は、ようやく慣れ始めた森辺の民との生活から、町へと進出する場面。
主人公のアスタにとって、町で料理を振る舞うのは、
「疎まれている森辺の民の地位向上のため」!
お金を稼ぐことも、もちろん大事!
森辺の狩人が狩る「ギバ」の肉の有用性を示せれば、それだけギバ肉の価値が高まり、
金銭的に厳しい生活を送っている森辺の民の生活が、少しずつ改善されていく。
それと同時に、滅多に町へ出ない森辺の民が、町で商売することで、
「森辺の民とはこういう性質の存在なのか」
と、町の人間との溝を埋める一助になる。
そんな、未来のために動くアスタたちには、勇気と元気をもらえます!!
この本は
・料理で未来を拓いていく物語が好きな人
・濃厚な人間模様が読みたい人
・明日への活力が得たい人
におすすめな作品です!


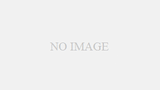
コメント