
こんにちは、てつやまです。
このたび、EDAさんの異世界料理小説
『異世界料理道⑪』を読みました。
《作品情報》
・書名 異世界料理道⑪
・著者 EDA
・出版社 株式会社ホビージャパン
・頁数 331
1.この本のここが凄い!
「異世界×料理」というのは、珍しいものではありません。
しかし、本作品が他の料理ファンタジー小説と違うのは、「チート」が全くないこと!
一つ一つ、異世界の食材と、見知った現代の食材を照らし合わせ、試行錯誤で料理していく。
そうして、料理を通じて、人と人の縁を紡ぐところが、ハートフル!
なぜこの本を読んだのか
他作品よりも、リアルに描かれた異世界料理小説だったから読み進めました。
没入しながら読むことができ、主人公とともに成長できる作品。
2.かんたんあらすじ
異世界に迷い込んだ少年が、料理の腕で、森辺の民と呼ばれる狩人の部族たちとの縁を結んでいく話。
11巻は、城下町への誘拐編。
心に響いたフレーズ
あれこれ煩悶しつつも、俺は調理で手は抜くまいという意気込みでこの場に立っていた。
主人公、アスタの心意気や気質を言い表したモノローグ。
たとえ無理やり連れてこられた身であったとしても、
「料理することにおいては、真剣に行うべきだ」
というモットーや誠実さを感じます。
もし、私が無理やり連れてこられ、幽閉されていたならば、とても相手のために何かをしようという気持ちは起きないと思いました。
しかし、主人公のアスタにとっての料理は、どんな悪人に対しても平等に応じるべきものなのだな、と感じました。
料理人としての信念を貫く名場面。
俺が料理を届けたい相手はアイ=ファなのだ。森辺の民なのだ。宿場町の人々なのだ。この場で得た技術や知識は、いずれみんなにも披露することができる
主人公の悲痛な想いと、一握りの希望にすがる様子。
豪華な食材、数多くの調理用具。
そんなものがいくらあっても、ただ単調に料理を作るだけの生活には耐えられない。
食べてもらいたい人に、自分が美味しいと思うものを振る舞い、その嬉しそうな顔、喜ぶ顔を見る。
そのこと自体に、自分も喜びを感じるのだ。
料理はアスタにとって、生きがい(=生きる目的の大きな一つ)であるという、強い意志を感じました。
「人間には、寄り添う相手が必要なのだ。……それさえあれば、どのような苦境でも強く生きていくことはできよう。」
伯爵令嬢リフレイアのために、罪を犯したサンジュラ。
それを告白して捕まった彼のことを、信頼を裏切られてもなお心配するアスタ。
そんなアスタに、アイ=ファは、この言葉で慰めます。
「アイ=ファにとっての父親。そして今は、アイ=ファにとってのアスタ。それが、サンジュラにとってのリフレイアであるならば、どんな困難な道でも強く生きていくことができる」
普段無口であるアイ=ファですが、何も考えていないわけではなく、寡黙な心の内では、言葉にできたに激情を抱いている。
そんな、作者の強い想いを感じました。
この本が気になった方は、是非下記リンクからご確認ください!
↓
3.まとめ
読んだことで得られたポイント
主人公アスタにとって、料理は、どんな状況でも手を抜かず、心を込めて届けたいという信念の象徴。
ときには幽閉されながらも、料理で人の心を動かすことを諦めず、
「食べてもらいたい人」のことを考えて料理する様子がとても印象的でした。
一方で、森辺の民に敵対する?伯爵家の動き。
その描き方に、ただの料理ファンタジーでは終わらない深みを感じました。
囚われの身でも希望を捨てないアスタに、困難に立ち向かう勇気をもらって気がします。
この本は
・信念を貫く主人公に元気をもらいたい人
・丁寧な仕事こそが信頼につながると信じる人
・“縁”や“信念”の力で逆境を越える物語が読みたい人
におすすめな作品です!


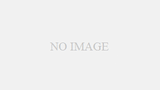
コメント