
こんにちは、てつやまです。
今日紹介する1冊はこちら
『「判断するのが怖い」あなたへ』佐藤恵美

本書は、「判断するのが怖い」という心理と、
発達障害特性のかかわりについて説明した本です。
どんな特性が「生きづらさ」に影響を与えているのか。
その特性により陥りがちな心理としてしまいがちな行動はなにか。
「判断」への不安を軽くするための具体的方策も提示・解説された本です。
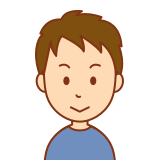
なんでこの本を読んだの?

タイトル『「判断するのが怖い」あなたへ』が、
まさしく自分のことを言っていると感じて、読んでみたくなりました。
また、発達障害特性の診断を受けているので、
「発達障害」というキーワードが含まれた本にはもともと興味がありました。
本の内容で大事な3つのポイント
①「判断するのが怖い」のはなぜ?
②「判断する」に必要な「だいたいこのくらい」感覚
③「判断する」への恐怖から自分を守る方法
一つずつ解説していきます!
①「判断するのが怖い」のはなぜ?
発達障害特性と「判断を恐れる気持ち」の関係
本書を読み進めていくうちに、まず「判断するのが怖い」という感情の背景には、
発達障害の特性が深く関わっていることがわかりました。
著者は、発達障害特性として
「部分」から「全体」を推し量る(想像する)ことが苦手で、
どうしても細やかな「部分」に注意が向いてしまいがちだと説明しています。
判断するためには、
「①情報の入力(インプット)」
「②情報の処理」
「③情報の出力(アウトプット)」
という3つの段階を経る必要があります。
しかし、発達障害特性を持つ人は、この「①情報の入力」の段階で既に困難に直面します。
部分から全体を想像することが苦手なため、仕入れる情報が一部分に偏り、
結果として偏った視点からの判断を余儀なくされてしまうのです。
さらに「細部へのこだわりが強く、それ以外のところには関心が向かない」
という極端な思考に陥りやすい性質も把握への障壁となります。
こうした特性から、全体像を把握できないまま判断を迫られる状況は、
大きな不安や恐怖を生み出します。
準備過剰やシミュレーションを繰り返しがちが理由で判断が怖くなる
もう一つの要因として、
「初めてのことはハードルが高く感じる」という特性があります。
未知の状況に対する不安から、あれもこれも準備しなければと強迫観念に襲われがちとなる性質をもっているのです。
本書の中で著者自身も、仕事で初めて行く場所へは事前に一度実際に行ってみなければ落ち着かず、不安であれこれ考えすぎていた経験を語っています。
先のことは推測はできますが不確定なもの。
それにもかかわらず、発達障害特性を持つ人は先取りした不安を頭の中から消すことができず、
シミュレーションを繰り返してしまいます。
この「わからない」ことへの耐性の低さが、判断への恐怖を増幅させているのです。
②「判断する」に必要な「だいたいこのくらい」感覚
なぜ「だいたいこのぐらい」という感覚が必要なのか?
判断を行う上で重要なのが「だいたいこのくらい」という感覚です。
しかし、発達障害特性を持つ人にとって、この曖昧な「だいたい」を把握することが
非常に難しいのです。
上司から「優先順位をつけろ」とか「完璧主義だ」などと言われることがある人は、
まさにこの「だいたいこれくらい」を把握することが苦手で、
かつ「こだわり」もあるため、成果物のボリュームや精度に周囲の期待との相違が生じたり、
提出時期が大幅に遅れたりすることになりがちです。
全体を把握していないと、
「どのくらい時間がかかり、どの方向性の判断になりそうか」
など見通しを立てられません。
優先順位をつけるためには、まず全部の項目を出して並べ替えていく必要がありますが、
部分だけを見ていて他を見ていなければ、当然並び替えることも不可能です。
そして、「全部の項目」を出すためには「だいたいこれくらい」という目安が必要で、
それがわからないため、いつまでたっても項目が出そろわず、
「完璧主義」だと周囲から言われてしまうのです。
この悪循環から抜け出すためには、「だいたいこれくらい」を類推する練習が必要になります。
「だいたいこれくらい」感覚を鍛える方法
本書では「だいたいこれくらい」感覚を養うための方法として、以下のような工夫が提案されています:
- 周囲の人の基準を観察する:同僚がどの程度の量や質の仕事をしているかを意識的に観察する
- 直接聞いてみる:「これくらいで良いですか?」と上司や同僚に確認する勇気を持つ
- タイムボックスを設ける:「この作業には2時間だけ」というように時間を区切る
- テンプレートを活用する:過去の事例や他の人の成果物を参考にする
これらの方法を実践することで、少しずつ「だいたいこれくらい」の感覚を身につけていくことができるのです。
③「判断する」への恐怖から自分を守る方法
「特性」・「心理」・「行動」を切り分ける!
本書で特に印象的だったのは、
「障害特性」
「そこから生まれる心理(気持ち)」
「そしてその心理に影響されて生じる行動」
を、きちんと分けて考える必要がある、という視点です。
「障害特性」は生まれ持ったものであり、自ら変えることはできません。
しかし、その特性から生じる「心理」や「行動」は、自分自身が創り出すものなので、
自らが変えることができるのです。
大事なのは
「自分の特性から生じる心理や行動を、どう変えていけば、生きやすくなるのか」
を考えることです。
切り分けるための具体的ケース
「だいたいこれくらい」がわからない
例えば、「だいたいこれくらい」がわからない場合:
- 曖昧なことを理解することが苦手だというのが「特性」
- その結果、周りよりも理解力が劣っていると自己嫌悪するのが「心理」
- そして、人と比べられる(自分でも比べてしまう)ことで人間関係がおっくうになり、コミュニケーションをとらなくなる、というのが「行動」
特性として曖昧なものを理解することが苦手なのは事実ですが、
それを得意に変えようとしても難しい。
しかし、心理として自己嫌悪することに気づいたり、行動としてコミュニケーションを避けるのは、
自分でコントロール可能な領域なのです。
人間関係を避ける
発達障害特性から生じる「陥りがちな心理、してしまいがちな行動」のひとつに
「人間関係を避ける」ことがあります。
「なんとなく仕事でうまくいかない」状態が続くと、あきれられたり叱責を受けたりして、
人間関係がおっくうになりがちです。
また、意見を否定ばかりされると、「自分の人格まで否定されている」と感じ、
自己肯定感が育たず、人とのコミュニケーションを避けるようになります。
このような悪循環から抜け出すために、本書では以下のような方法が提案されています:
- 自分の特性を知る:まずは自分にどのような特性があるのかを理解する
- 特性から生じる心理と行動を具体化する:自分の中でどのようなストーリーが起きているのかを把握する
- 心理面へのアプローチ:マインドフルネスやアンガーマネジメントなどで心理的な負担を軽減する
- 行動面へのアプローチ:アサーション(自分も相手も大切にした伝え方)などのコミュニケーション技術を学ぶ
- 環境調整:自分に合った環境や条件を整える
職場での自己開示はよく考えて伝えるが吉!
また、職場での自己開示についても触れられており、
「業務遂行をスムーズにするため」というスタンスで、
何をどうしたらよいのかという具体策を伝えることの重要性が説かれています。
単に「発達障害です」と伝えるのではなく、
「このような環境や対応があれば、より良いパフォーマンスを発揮できます」
という建設的な提案をすることが大切なのです。
コミュニケーションの工夫【二者択一を超えて考える】
判断の恐怖からしばしば生まれる問題として、コミュニケーションの難しさがあります。
本書では、
1.自分の主張を押し通して周囲から顰蹙を買う
2.我慢して自分の主張を完全に引っ込めて不満をため込む
という二者択一として捉える 危険性を示しています。
そして、そうではない方法があることを教えてくれます。
これはまさに、白黒思考の典型的な例です。
多くの人が、ハッキリ言うか、押し黙るかの二択でコミュニケーションを取っていますが、
どちらの方法でも、人間関係にしこりが残ってしまいます。
本書で紹介されている
「自分も相手も心地よいコミュニケーション【アサーション】」
は、この問題を解決する鍵となります。
他人の顔色ばかり見ていて
「こんなこと言ったら気まずくなるのでは」
という恐怖から言いたいことを飲み込み、限界まで飲み込んで爆発するというパターンから抜け出すためには、
相手を尊重しつつ自分の感情も伝える技術が必要なのです。
まとめ
繰り返しとなりますが、本書のポイント
①「判断するのが怖い」のはなぜ?
②「判断する」に必要な「だいたいこのくらい」感覚
③「判断する」への恐怖から自分を守る方法
「判断するのが怖い」という心理の背景には発達障害の特性があり、
それが行動にも影響し、人間関係の悩みを生む場合があります。
本書を通じて、特性・心理・行動をセットで具体化する重要性を学びました。
例えば、特性から生じる心理や行動には工夫が可能。
「細かいことに気づきやすい」という特性では、
心理的には「一旦忘れる工夫」、
行動面では「タイマーで強制終了」などがあります。
また、判断が怖いと感じる際、その基準が明確であれば苦手意識が軽減すると考えられます。
自身の特性に基づいたストーリーを作ることで、
生きやすさを向上させる第一歩となることを実感しました。
この本は
・自分が「発達障害」かもと悩む人
・職場の「発達障害特性を持っていそうな人」との付き合い方に悩む人
・「なんだか生きづらいな」とモヤモヤする人
におすすめな一冊です!
この本が気になった方は、是非下記リンクからご確認ください!
↓


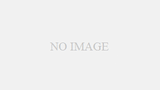
コメント