
こんにちは、てつやまです。
今日紹介する1冊はこちら
『マンガでわかる 適応障害』浅井逸郎(監修)/田中へこ(マンガ)

本書は、精神科医、浅井逸郎さんが監修している、マンガ ストーリー仕立てで、適応障害について学べる本。
適応障害と診断を下す上での条件など、詳しく解説されています。
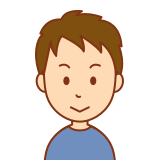
なんでこの本を読んだの?

私自身、広汎性発達障害と診断を受けています。
そして、発達障害と似た概念で「適応障害」という精神疾患があります。
この両者の違いを簡単に、分かりやすく知りたいと思い、本書を読んでみました。
本の内容で大事な3つのポイント
①適応障害は「心の弱さ」が原因ではない!
②ストレスとの付き合い方と「助けを求める力」
③自分に合う環境と回復のための工夫
一つずつ解説していきます!
①適応障害は「心の弱さ」が原因ではない!
適応障害は、「環境と自身の不一致」によって起こる
適応障害という言葉を聞いたとき、多くの人は
「軽いうつ病のようなもの」
「心が弱い人がなる病気」と誤解してしまいがちです。
しかし、この本を読んで、その認識がいかに危険で、当事者を追い詰めてしまうかを痛感しました。
適応障害とは、
ある状況や環境にうまく馴染めず、強いストレスを受け続けることで心身に不調が生じる病気です。
これは誰にでも起こりうるものであり、「心が弱いから」では決してありません。
例えば、真面目で責任感が強い人ほど、環境に馴染もうと無理をして限界まで我慢してしまうことがあります。
それが結果的に心身のバランスを崩す原因になるのです。
心の強さは、「耐える」ことよりも「感じて生きる」こと?
私自身、かつて「うつ病」と診断され退職した経験があります。
その時、心の中では
「周りはうまく働けているのに…」
「もっともっと、頑張らないと」と、自分自身を必要以上に鼓舞させていました。
心の強さ弱さとは、一体何でしょうか。
例えば、親しい友人が亡くなっても涙ひとつ流さないことが、「強さ」なのでしょうか。
それよりも、人の感情に共鳴できることこそが人間らしさであり、
その感受性を持ちつつ生きることこそ、本当の強さで、
それらによって、文化や社会は育まれてきたのだと思います。
いつ自分にも起こるかわからないもの
適応障害を理解することは、誰かが感じている「生きづらさ」を理解することに繋がります。
誰かの「生きづらさ」を考えるのは、なにも知らない状態より、よほどしんどいことでしょう。
しかし、その他人の「生きづらさ」は、実は自分とまったくの無関係ではありません。
なぜなら、適応障害は、「環境」の変化により、ひょんなことから当事者となるものだから。
だからこそ、他人の苦しみに対して「自分には関係ない」と突き放さず、
「誰にでも起こりうること」として、共感と支援を差し伸べることが大切なのだと思いました。
②ストレスとの付き合い方と「助けを求める力」
「助けを求める力」は生きる力
本書の中でとても印象的だったのは、適応障害と診断される人の多くが、
「誰かに助けを求める」ことが苦手であるという点です。
これは私自身にも思い当たる節があります。
辛い時こそ、誰かに頼らなければならないのに、
「迷惑をかけたくない」
「弱い自分を見られたくない」
という思いが邪魔をして、なかなか言葉にできないのです。
一人で抱え込まない「ストレスコーピング」
特に若い人たちは、ストレスに対する経験値が少なく、適切な対処方法を知らないまま悩み続けてしまうケースが多いのではないでしょうか。
本書では、ストレスにうまく対処する力、つまり「ストレスコーピング力」が未熟な状態であることが、適応障害の発症につながる可能性があると指摘しています。
たとえば、ある高校生が、部活動で先輩に強く叱責される経験をしたとします。
その子がその出来事を誰かに話し、気持ちを吐き出せれば、心は少しずつ落ち着いていくでしょう。
しかし、自分だけで抱え込み、「自分が悪い」と思い込むと、心の中にストレスが留まり続け、
眠れなくなったり食欲が落ちたりと、日常に支障が出始めます。
「助けて」は甘えではなく、生きる技術
「助けてほしい」と口に出すことは、決して甘えではなく、生きる上で必要な力です。
「助けて」という言葉は、自分ではどうしようもない時に必要になってきます。
しかし、自分ではどうしようもない、追い詰められた状態でこそ、「助けて」と言えなくなる人が多い。
だからこそ、元気な時こそ、「助けを求められる環境」を、整えておくことが大事。
自分の気持ちを言葉にすることは確かに難しいですが、
元気な時こそ自分の心の状態に気づく練習をすることで、
苦しい時にも一歩踏み出しやすくなるのではないかと感じました。
③自分に合う環境と回復のための工夫
「合わない場所」から離れる勇気が回復の第一歩
この本で、私が最も強く共感したのは、
「その人が良い人か悪い人かではなく、自分にとってストレスであるかが大事」
という部分です。
社会では「人間関係を築くことが重要」「我慢するのが大人の対応」とされることが多いですが、
無理をしてまで人間関係に適応しようとすることは、必ずしも正解ではありません。
たとえ、世間一般からどんなに優良だと思われていても、
「自分に合わない」と感じる場所に居続けることこそ、心をすり減らせることはないのです。
憧れの職業「公務員」が合わない人もいる
私自身、公務員として働いていた頃、部署移動を繰り返す中で
「どんな職場でも安定した成果を出すことが求められる」状況に苦しさを感じていました。
周囲からは「安定した職業で羨ましい」と言われたこともありました。
しかし、私にとっては、部署が変われば、常に環境が変化し、「変わった環境に全力で答えようとする生真面目さゆえに、精神的な負荷が高まる働き方」が、合っていなかったのだと思います。
「自分のつらさ」を優先してもいい
本書に登場する美咲さんも、上司が良い人であるにもかかわらず、その存在が自身のストレスになっていることに気づき、距離を取る決断をしました。
「良い人だから離れてはいけない」と思ってしまうと、自分の苦しみを、自分自身が認められなくなってしまいます。
しかし、心の回復のためには、自分の気持ちを最優先することが何より重要なのです。
「自分が安心できる環境」が一番大事
人気の部署や評価の高い職場でも、自分の適性に合っていなければ、ストレスは増していきます。
「評価が高い=自分にとって良い」とは限りません。
無理して働き続けるよりも、自分が安心して過ごせる環境を探すことのほうが、
よっぽど意味のあることだと、本書を通じて強く感じました。
まとめ
繰り返しとなりますが、本書のポイント
①適応障害は「心の弱さ」が原因ではない!
②ストレスとの付き合い方と「助けを求める力」
③自分に合う環境と回復のための工夫
この本を読んで、「適応障害=心が弱い」って思いこみが危ないことを再認識しました。
ストレスは誰にでもある。
そのストレスを抱えた中でも、「助けて」って言える力こそが本当の生きる力なんだと感じます。
頑張りすぎてしまう人ほど、自分に合わない環境で無理しがち。
大切なのは、評価や他人の目じゃなく、「自分が安心して過ごせる場所を選ぶ」こと。
自分の気持ちに気づき、言葉にする練習をしておくことで、辛いときにちゃんと自分を守れるんだなと学びました。
人の感情に共鳴できること、それを受け入れて生きることが、ほんとの強さなのだと思います。
この本は
・自分の気持ちを押し殺して頑張りすぎちゃう人
・公務員でも「本当に自分に合ってる?」と悩んでいる人
・「助けて」がなかなか言えない真面目な人
におすすめな一冊です!
この本が気になった方は、是非下記リンクからご確認ください!
↓




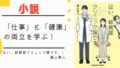
コメント