
こんにちは、てつやまです。
今日紹介する1冊はこちら
『バズる1行』中山マコト

本書は、「キャッチコピー」について書かれた本です。
「バズる」=爆発的な拡散力を持った言葉、
についての有用性と具体的な方法を解説しています。
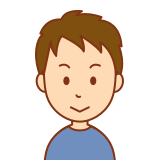
なんでこの本を読んだの?

人の心に残る言葉。
そのチカラのすごさを知っているから。
また、コピーライターという人が、どうやって
その「バズる言葉」を生み出しているか、
興味があったため、読んでみました。
本の内容で大事な3つのポイント
①キャッチコピーは「自分を守る盾」である
②「新しさ」や「初」をアピールする
③相手の立場になって考える
一つずつ解説していきます!
①キャッチコピーは「自分を守る盾」である
キャッチコピーは、「チャンスをつかむ力」を持っている!
「キャッチコピー」と聞くと、どんなイメージが浮かぶでしょうか?
商品の宣伝文句、SNSの目を引くフレーズ、あるいは企業のスローガン──。
多くの人は「人の目を引くための言葉」というイメージを持っているかもしれません。
しかし、中山マコトさんの『バズる1行』を読むと、キャッチコピーには
私たちが思っている以上の力があることに気づかされます。
本書によれば、キャッチコピーとは
「チャンスをキャッチする」もの
だと説明されています。
チャンスをつかみにいく「能動的」な力
私はこれまで、キャッチコピーとは単なる言葉、ただそこにあるだけで
「見つけてもらう」という受動的なものだと考えていました。
しかし実際は「チャンス」をキャッチしにいくという、能動的な存在だったのです。
この視点の転換は私にとって大きな発見でした。
ただ漫然と言葉を繰り出すだけでは、本当の意味でバズる1行は生まれないのだと痛感しました。
チャンスをつかめるように、キャッチコピーを作る──
この姿勢が重要なのです。
行動理念を貫く根幹を授けるもの
さらに興味深いのは、キャッチコピーが「自分を守る盾」になるという指摘です。
本書では次のように述べられています。
「キャッチコピーを持っていなければ、断るのは大変。こちらに大義がないですからです。
でも、『キャッチコピー=バズフレーズ』を持っていれば、それはある意味、錦の御旗になります
『こう言っちゃってるんでルールは破れないんですよ。申し訳ないです』
とまさに踏み絵の役割を果たしてくれるのです」
つまり、キャッチコピーには自分の芯を作る役割があるのです。
自分の行動理念を表したキャッチコピーは、その行動理念を貫く力を与えてくれます。
そして対外的にも「こう言っているので変えられない」と、
相手の無理な要望を断ることもできる。
自分を保ち続けるための一つのテクニックと言えるでしょう。
頼みごとを断る時の強い味方になる!
例えば「丁寧な仕事にこだわります」というキャッチコピーを掲げている人なら、
納期が迫っているからといって妥協した仕事を求められたときに
「私は丁寧な仕事にこだわると宣言しているので、それができない仕事はお受けできません」
と断る方法もとれます。
これは単なる言い訳ではなく、自分の価値観を守るための盾なのです。
私自身も、何か断りづらい頼みごとをされたとき、「すみません、自分のポリシーで…」と言って断った経験があります。
しかし、その「ポリシー」が明確な言葉になっていなかったため、相手に伝わりづらかったことも事実です。
中山さんの言う「バズフレーズ」として自分の信条を言語化しておくことで、
より明確に自分の立場を示せるのだと理解しました。
②「新しさ」や「初」をアピールする
「新しさ」とは、「相手にとっての」新鮮さ
本書の中で特に印象的だったのは、「新しさ」を強調することの重要性です。
さらに著者は、
「ここでいう新しさとは、『新しく感じられる』ということです」
と指摘を強調しています。
つまり、客観的に革新的である必要はなく、受け手にとって新鮮に感じられることが大切なのです。
よく広告などで「本邦初公開!」という表現を目にしますが、このような言葉を使うと、
「何か特別なことにしか適用できない」ように思え、まねできそうにないように感じます。
しかし実際には、「初めてこの小説の感想を語る!」「幼少期好きだった漫画はこれ!」など、
私たちが公開していない情報は山ほどあるはずです。
「初」の力を利用する!
何事も「初」と銘打てば、なぜかそれだけで貴重なものに感じられる力があります。
これは人間の心理として、「初めて」という言葉に価値を見出す傾向があるからでしょう。
新製品に飛びつく消費者心理も、この「新しさへの渇望」から来ているのかもしれません。
考えてみれば、私たちの日常生活でも「初」という言葉の威力は絶大です。
「初デート」「初給料」「初著書」など、同じ経験でも「初」がつくことで特別な輝きを放ちます。
SNSでも「初投稿」や「初めて〇〇してみた」という投稿は注目を集めやすいものです。
著者の中山さんは、この「初」の力を活用すべきだと教えてくれます。
自分自身の経験や考えを発信するとき、それが「初めて」のものであることを強調するだけで、
より多くの人の目に留まりやすくなるのです。
例えば、ブログを書くなら「私が初めて挑戦した料理のレシピ」「この映画の魅力を初めて語ります」など、「初」という言葉を前面に出すことで読者の興味を引くことができます。
たとえ小さなことでも、それが「初」であれば価値が生まれるのです。
「自分の視点」も「誰かにとって」新しい
また、これは単に目新しさを追求するだけではなく、自分自身の経験や視点の価値を再認識することでもあります。
私たちは自分の考えや経験を当たり前だと思いがちですが、
実はそれが誰かにとっての「初めて知る情報」かもしれないのです。
そういう自分の視点が、誰かの役に立ったならば、とても喜ばしいことだと思います。
③相手の立場になって考える
相手の立場になって、関心を引く言葉を狙い撃つ!
本書で最も重要なメッセージの一つが、「相手の立場になって考える」ことの大切さです。
著者の中山さんは、「ハイパー・バズフレーズ」について、
「相手が欲しいであろうもの、関心を示すであろうこと」を想定し、待ち伏せする言葉
だと説明しています。
この考え方は、前述した「キャッチコピーとは、チャンスをキャッチするもの」という定義と密接に関連しています。
このチャンスとは「相手が欲しいであろうもの」「関心を示すであろうこと」に他なりません。
つまり、相手の身になって、相手の考え方をトレースし、興味関心ごとを絞り込むことが大切なのです。
そして、その興味関心ごとへの答えや対策を提示する──
これがバズるキャッチコピーを生み出す基本的な方法論となります。
「ハイパー・バズフレーズ」とは「魚釣り」である
これは魚釣りに似ています。
海にいる魚、川にいる魚、口の大きさ、動きの速さなど、
魚によって性質が異なるように、人によって興味関心を引くキャッチコピーも異なります。
小学校の時に先生から「相手のことを考えなさい」と教わったことが、このような形で生きてくるとは思いませんでした。
例えば、若者向けの商品なら「SNS映え抜群!」「手軽に本格的」といったフレーズが効果的かもしれません。
一方、中高年向けなら「昔ながらの安心感」「長く使える確かな品質」といった言葉が響くでしょう
同じ商品でも、訴求するターゲットによってキャッチコピーは変わってくるのです。
キャッチコピーには「実力」と「責任」が伴う
しかし、ここで重要な注意点があります。
著者は「名乗った以上は、本物でなくてはいけない!」と強調しています。
つまり、相手の興味関心ごとへの答えをキャッチコピーにする場合、
実際にその答えを提供できる実力がなければならないのです。
実力不足で答えを提供できない場合、できないことをできると言うのは相手を騙す行為になりかねません。
強い言葉を使うには、実力、経験、そして責任が問われます。
「日本一の〇〇」「最高の△△」といったキャッチコピーを使う場合、本当にそれに見合う価値を提供できるのか、自問自答する必要があります。
「相手に響く」と、「誠実に伝える」のバランスが重要!
このキャッチコピーで、自分が本質以上に見られることはないだろうか。
自分がこのキャッチコピーを見て、期待して行動した結果、成果があったと満足できるだろうか。
他者の考え方をトレースするのと同時に、「自分だったらどうだろう」という自分事として考えるバランスが大切です。
これは単なるマーケティングテクニックを超えた、
誠実なコミュニケーションの本質に関わる問題です。
バズを追求するあまり、嘘や誇張に頼ってしまっては本末転倒。
相手の立場に立ちつつも、自分の真実を伝えるという難しいバランスが求められるのです。
まとめ
繰り返しとなりますが、本書のポイント
①キャッチコピーは「自分を守る盾」である
②「新しさ」や「初」をアピールする
③相手の立場になって考える
『バズる1行』を通して、中山マコトさんは、単なるテクニックを超えた、言葉の本質的な力を教えてくれます。
キャッチコピーは「自分を守る盾」となり、「新しさ」を強調し、「相手の立場に立って」考えることで真の力を発揮するのです。
キーワードは「誠実さ」。
どれだけ巧みな言葉を操っても、その裏に実力や真実がなければ、長続きはしません。
バズるフレーズを生み出すことは、自分自身を深く理解し、他者の心を想像する力を養うことでもあります。
日常生活でも、SNSでの発信でも、仕事のプレゼンでも、「バズる1行」の考え方は活かせるはずです。
自分の芯となる言葉を持ち、新しい視点を提供し、相手の立場に立って考える──
この三つの原則を意識するだけで、私たちのコミュニケーションはより豊かなものになるでしょう。
最後に、本書から学んだ最も重要なことは、言葉の力を信じることです。
適切な言葉は、単なる情報伝達を超え、人の心を動かし、行動を変え、時には人生さえも変えることができます。
日々の会話や発信において、この言葉の力を意識して活用していきたいと思います。
私自身も、この本を読んだ後、自分の発信を見直してみました。
そうすると、これまで漠然と言葉を選んでいた部分が多々あったことに気づきます。
これからは
「自分の芯となる言葉は何か」
「相手は何を求めているのか」
「どのような新しい視点を提供できるか」
を問いながら、一語一語を大切に選んでいきたいと思います。
この本は
・受け身な性格の人
・言葉のチカラを知っている人
・自分の強みをもっとアピールしたい人
におすすめな一冊です!
この本が気になった方は、是非下記リンクからご確認ください!
↓


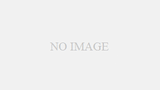
コメント