
こんにちは、てつやまです。
今日紹介する1冊はこちら
『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』三宅香帆

本書は、タイトルの通り「なぜ働いていると本が読めなくなるのか」という問いに、著者が考え抜いた本。
読書と労働の関係性を、時代の流れに合わせて解説。
「歴史上、日本人はどうやって働きながら本を読んでいたのか?そしてなぜ現代の私たちは、働きながら本を読むことに困難を感じているのか」という問いについて考えた本。
(本書より抜粋)
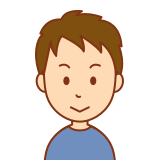
なんでこの本を読んだの?

読書が趣味。
しかし、働いていた時は、確かに読書量は減っていました。
正確には、「余暇における読書の割合」が、減少。
タイトルの通り、何故働いていると本が読めなくなるのか、が気になり、
読んでみたくなりました。
本の内容で大事な3つのポイント
①時代とともに変わる読書の形 – 教養からハウツーへ
②「ノイズ」と読書の価値 – 予測不能な出会いの醍醐味
③「知識」と「情報」の違い – ノイズの価値を見直す
一つずつ解説していきます!
①時代とともに変わる読書の形 – 教養からハウツーへ
「教養」から「スキルの習得」や「娯楽」へ
「なぜ働いていると本が読めなくなるのか」
── この問いかけは、ただの時間不足の話ではありません。
この本の著者、三宅香帆さんは、読書と労働の関係性を時代背景とともに
深く掘り下げています。
かつて読書とは、インテリ層や富裕層のステータスでした。
「あの人は教養がある」という評価につながる行為であり、一般の人々には遠い存在でした。
しかし、高度経済成長の中で、サラリーマンが爆発的に増加し、
読書の主な担い手がこのサラリーマン層へと移行したのです。
サラリーマンが増えたなら、彼らに向けた本を出せば売れるはず
──そう考えた出版社は、余暇時間の少ないサラリーマン向けに、
「英語力」や「記憶力」を向上させるハウツー本や、
読みやすく身近なサラリーマン小説を誕生させました。
こうして読書の目的は「教養を身につける」ことから
「仕事に役立つスキルを学ぶ」「限られた時間で楽しむ」へと多様化したのです。
身近になった「読書」
本との出会い方も大きく変わりました。
かつては書店に行かなければ本を手に取る機会はありませんでした。
しかし、それが今では、テレビで紹介されたり、SNSで話題になったり、
インターネット上のレビューを見たりと、本との出会いは無限に広がっています。
この変化により、読書は富裕層やインテリ層だけのものではなく、
誰もが身近に触れられるものになりました。
私自身、富裕層やインテリ層ではないので、この時代の恩恵を有難く享受しているなと感じます。
本との出会いの場が増えたことで、より多くの人が、
様々なジャンルの本に触れられるようになったのは素晴らしいことだと思います。
②「ノイズ」と読書の価値 – 予測不能な出会いの醍醐味
「ノイズ」を除去するか、提示するか
本書で特に印象的だったのは、「ノイズ」という概念です。
著者によれば、「ノイズ」とはコントロールできないもの、予測できない要素を指します。
そして現代社会では、このノイズを除去し、効率よく情報を得ることが重視される傾向があります。
自己啓発書の特徴は、まさにこの「ノイズを除去する」姿勢にあると著者は指摘しています。
他人や社会といったコントロールできない要素は捨て置き、
自分でコントロール可能なものに注力すべきというのが、自己啓発書の基本的なスタンスです。
一方で、文芸書や人文書といった、社会や感情について語る書籍は、
むしろ人々にノイズを提示する作用を持っています。
例えば、ミステリ小説を考えてみると分かりやすいかもしれません。
犯人を当てる、トリックを解明する、動機を理解するといった目的は様々ですが、
その過程を楽しむのがミステリの醍醐味です。
もし「ノイズを除去する」ことだけを重視するなら、冒頭で犯人を提示し、
トリックのタネを明かし、動機をすぐに披露すればいいでしょう。
最終的に得られる情報だけを見れば、「ノイズ」を除去してもしなくても同じです。
しかし、それは何だか、感覚的におかしいと感じる。
このなんとも言えない気持ち悪さこそが、読書が「ノイズを除去した情報」のみを得るための行為ではないことの証拠だと思います。
タイパ重視か、エンタメ重視か
昨今、「ドラマの倍速視聴」や「小説の結末を先に確認する読み方」など、
「話の流れ」という情報さえ抑えられればいいという考え方が生まれています。
「時は金なり」のタイムパフォーマンスを重視する現代人にとって、自分でコントロールできない展開に時間を費やすことは無駄に思えるのかもしれません。
しかし著者は、読書とは
「何が向こうからやってくるのか分からない、知らないものを取り入れる、
アンコントローラブルなエンターテインメント」
だと捉えています。
知らないものを取り入れる楽しみ方もあれば、知っている結末への過程を楽しむ方法もある
──どちらが正しいということではなく、「求めるものが異なる」。
それだけの話 なのだと思います。
③「知識」と「情報」の違い – ノイズの価値を見直す
「情報」とは、「知識」から「ノイズ」を取り除いたもの
著者は「知識」と「情報」を明確に区別しています。
読書して得る「知識」にはノイズ──偶然性が含まれます。
教養と呼ばれる古典的な知識や、小説のようなフィクションには、
読者が予想していなかった展開や知識が登場します。
一方、「情報」にはノイズがありません。
なぜなら、情報とは読者が知りたかったことそのものを指すからです。
著者の言葉を借りれば、「情報とは、ノイズが除去された知識のこと」なのです。
だからこそ、「情報」を求める人に「知識」を渡そうとすると、
「その周辺の文脈はいらない、ノイズである、自分が欲しいのは情報そのものである」
と言われるでしょう。
これは決して悪いことではありません。
タイムパフォーマンスを求める現代人には、結論は何かを、先に提示することが大事だと、私も思います。
そのあとの「ノイズ」、文脈の詳細は、見たい人だけ見ればいい、というスタンスもストレスが少ないやり方かもしれません。
「何事も経験」スタイルで、「ノイズ」も享受する
ただ、だからと言って何でもかんでも ノイズを除去することが正しいというわけではないと考えます。
私の父親はよく「何事も経験」という言葉を口にします。
これは、まさに「ノイズを除去しない」というスタンスです。
情報のみではなく、それに付随している文脈をも取り入れることが、人生をより豊かにするという考え方。
わからないものに出会う。
それによって人としての深みが増す。
自分自身を苦しめない限りは、「未知」とは喜ばしいものなのかもしれません。
読書とは「他者の文脈に触れる」こと
本を読むと、他者の文脈に触れることができます。
自分から遠く離れた文脈に触れること
──それが読書の本質だと著者は語ります。
この「文脈」という言葉には、「人生」「経験」「体験」「考え方」「趣味嗜好」などが含まれると感じました。
役に立つ情報を簡単に得ることが求められる労働環境では、この「文脈」は「ノイズ」であり、余分なものとされます。
そして「読書」にはノイズが含まれている。
だからこそ、労働と読書の両立が困難なのです。
「自分から遠く離れた文脈」は、労働を前にしたら後回しになり、
「自分に近い役に立つ情報」の方が重要視されるのです。
まとめ
繰り返しとなりますが、本書のポイント
①時代とともに変わる読書の形 – 教養からハウツーへ
②「ノイズ」と読書の価値 – 予測不能な出会いの醍醐味
③「知識」と「情報」の違い – ノイズの価値を見直す
本書「なぜ働いていると本が読めなくなるのか」は、
単に時間の問題を論じるのではなく、読書と労働の本質的な関係性に迫った一冊です。
サラリーマンの増加により、読書の目的は「教養」から「実用」、「娯楽」へと多様化しました。
本との出会い方も書店だけでなく、テレビやインターネットなど広がりを見せています。
一方で、「ノイズを除去」し効率を重視する現代社会においては、
未知の要素を楽しむ読書の価値が見失われがちです。
自己啓発書はノイズを除き、効率よく知識を伝える一方、
小説や文芸書はノイズを受け入れることで、予想外の学びや感情を引き出します。
しかし現代の効率重視の社会では、このノイズを避ける傾向があるのです。
「働きながら本が読める社会」とは、ノイズを恐れず、未知なるものとの出会いを楽しめる
余裕のある社会なのだと思います。
仕事の効率と読書の豊かさ、両方を大切にする心地よいバランスを見つけることが、
現代を生きる私たちに求められているのではないでしょうか。
この本は
・読書が趣味な人
・「情報の速さ」に疲れている人
・労働と趣味のバランスを考えている人
におすすめな一冊です!
この本が気になった方は、是非下記リンクからご確認ください!
↓



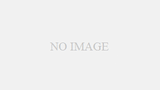
コメント