
こんにちは、てつやまです。
今日紹介する1冊はこちら
『親の見守り・介護をラクにする道具・アイデア・考えること』工藤広伸

本書は、「道具を通じて」親の自立を引き出しながら元気で長生きしてもらい、介護する子がストレスなく過ごすための工夫を紹介した実践本。
著者の「道具がどれだけ自分の介護を救ってきたかを伝えたい」という熱意が込められた本です。
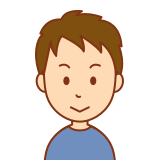
なんでこの本を読んだの?

私自身、遠くに両親が住んでいるため、「離れて暮らす親を支える方法」には興味があり、読んでみたくなりました。
また、著者自身の、介護における工夫を知ることができそうだと感じたため、読んでみました。
本の内容で大事な3つのポイント
①道具の力を最大限活用しよう
②みんなで支える仕組みづくり
③「専門家を頼る」重要性
一つずつ解説していきます!
①道具の力を最大限活用しよう
親の自立と子の負担軽減の一挙両得を目指す意味
「親の介護は愛情と忍耐で乗り切るもの」
—このような考え方は、介護する側に大きな負担を強いることになります。
本書では、適切な道具を活用することで、親の自立を促しながら
介護者の負担を大幅に軽減できると説きます。
御飯をいつも多く炊いてしまう場合
たとえば、認知症の親が、子供が育ち盛りの時のように
「いつも通り3合炊く」習慣から抜け出せないケース。
その結果、余ったご飯を毎日捨てるハメに…
これは一見したところ大した問題ではないように思えます。
しかし著者は、このような「無意味な行為」の積み重ねが、介護者に
「無理」
「無茶」
「無駄」
という負の感情を蓄積させる危険性を指摘します。
解決策は「1号炊き炊飯器」
解決策は意外にもシンプル。
3合炊きから1合炊きのサイズの小さい炊飯器に切り替えるだけ。
これで、食べきれる量だけを炊くことができるようになります。
この一例だけでも、適切な道具選びがいかに重要かがわかります。
私自身も、実家の母が父と二人暮らしなのに、毎日習慣的にご飯を炊いている様子を思い出しました。
私の母親は、まだ認知症ではないと思いますが、長年の習慣は簡単には変えられないもの。
将来的に同じような問題が起きる可能性は十分にあります。
早めに小さい炊飯器を提案してみようと思いました。
このように、日常生活の細部において適切な道具を取り入れることで、親の自立を促しながら介護者の負担を軽減できるのです。
著者は、介護用品だけでなく一般的な家電製品や日用品においても、
親の状態に合わせた選択が重要だと強調しています。
②みんなで支える仕組みづくり
介護は一人で抱え込むものではない
本書の中で特に印象的だったのは
「介護は一人で抱え込むものではない」
という視点です。
従来のイメージでは
「親の面倒は子どもが見るべき」という価値観が強調されがちですが、
著者はそのような考え方こそが介護を困難なものにしていると指摘します。
大切なのは
「親の介護が無理なく回る」こと。
そのためには、子ども一人が負担を強いられる方法では、持続可能ではありません。
介護する子どもも、心身ともに健康であってこそ、親の介護も無理なく続けられるのです。
道具も大切な「仲間」
この「無理なくまわる」仕組みづくりにおいて、道具は重要な「仲間」になります。
例えば、見守りセンサーやGPS機器は、認知症の親の安全を確保しながら、
介護者の負担を大幅に軽減できます。
また、入浴や排泄の介助器具は、親の尊厳を守りつつ、介護者の身体的負担を軽減してくれます。
自分がいなくても回る介護=親のため
さらに著者は
「自分がいなくても介護が回る状態」
を目指すべきだと説きます。
これは一見すると冷たい考え方のように聞こえるかもしれませんが、実は親のためでもあるのです。
なぜなら、介護する側が過労で倒れてしまえば、最終的に困るのは親自身だから。
この視点は私に大きな気づきを与えてくれました。
「愛情があるなら自分の手で介護すべき」という考えに縛られず、
専門家や適切な道具の力も借りながら、持続可能な介護の仕組みを作ることこそが、
本当の意味で親を大切にすることなのかもしれません。
③「専門家を頼る」重要性
なぜ専門家の意見を頼るのか?
本書が強調する、もう一つの重要なポイントは、福祉用具の選択において
「専門家の知見を活用することの大切さ」です。
著者は
「家族自身が福祉用具を選ぶのではなく、プロである専門相談員に選んでもらい、用具の選択ミスやムダな出費をしないように」
と助言しています。
福祉用具の世界は素人には複雑すぎます。
「安いから」「便利そうだから」という主観的判断で選ぶと、実際の介護現場では役に立たないこともしばしば。
福祉用具の専門家たち
そこで力を発揮するのが、福祉用具の専門家である
「福祉用具相談員」
「福祉用具プランナー」といった専門家たちです。
彼らは単に商品を販売するだけでなく、親の状態や住環境、介護者の状況などを総合的に判断して、最適な福祉用具を提案してくれます。
本書によれば、特に経験豊富な福祉用具相談員は、介護現場での実績に基づいた、
貴重なアドバイスを提供してくれるそうです。
専門家選びのコツは「ケアマネジャー」
ただし、専門家選びも難しいもの。
そこで著者は、まずケアマネージャーに相談し、
信頼できる福祉用具専門家を紹介してもらうことを勧めています。
介護のプロフェッショナル同士のネットワークを活用することで、
より質の高いサポートを受けられるというわけです。
福祉用具「レンタル」のメリット
特に印象的だったのは、福祉用具の入手方法として「レンタル」のメリットを強調している点です。
認知症のように状態が変化する場合、
一度購入した用具が数ヶ月後には不適切になることもあります。
レンタルであれば、親の状態変化に応じて柔軟に用具を入れ替えられるため、
結果的にコスト面でも効率的です。
もちろん、肌に直接触れる入浴用具や排泄介助用具などは衛生面から購入が必要ですが、
それ以外の多くの福祉用具はレンタルで対応できます。
私自身、将来の親の介護に備えて、この「購入かレンタルか」の選択基準は非常に参考になりました。
まとめ
繰り返しとなりますが、本書のポイント
①道具の力を最大限活用しよう
②みんなで支える仕組みづくり
③「専門家を頼る」重要性
私自身、この本を読むまでは「介護=人の手による世話」というイメージが強かったです。
しかし、本書を通じて、適切な道具の選択と専門家の活用が、親と介護者双方のQOL(生活の質)向上に繋がることを学びました。
「道具に頼る=手抜き」という考え方から脱却し、「道具も大切な介護の仲間」と捉え直すことで、介護に対する心理的負担も軽減できると学びました。
この本は
・親の介護に不安を抱いている人
・親と別々に暮らしている人
・「介護に役立つ道具」に興味がある人
におすすめな一冊です!
この本が気になった方は、是非下記リンクからご確認ください!
↓



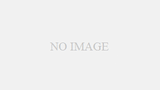
コメント