
こんにちは、てつやまです。
このたび、新名智さんのミステリー小説
『雷龍楼の殺人』を読みました。
《作品情報》
・書名 雷龍楼の殺人
・著者 新名智(にいなさとし)
・出版社 角川書店
・頁数 282
- 1.この本のここが凄い!
- 2.かんたんあらすじ
- 心に響いたフレーズ
- これより油夜島で起きる連続殺人事件の犯人は、外狩詩子ただひとりである。疑り深い読者のため、ここにはなんの叙述トリックも存在しないと付け加えておこう。外狩康弘を殺すのも、上田香と泰造の夫婦を殺すのも、小林健吾を殺すのも、すべて詩子ひとりが計画し実行するという意味であって、それ以外の解釈はない。
- にぃには島へ行ってしまった。ということは、ここへ助けには来られない。自分でなんとかするしかない。
- 「ろくな動機もなしに人を殺す人間はたくさんいるし、明確な動機があっても人を殺さない人間はもっと大勢いる。~犯人は、なんとなく四人を殺したのかもしれないし、周囲の人間には理解できない恨みがあったのかもしれないし、もちろん現実的な損得勘定が働いたのかもしれない。」
- 心に響いたフレーズ
- 3.まとめ
1.この本のここが凄い!
安楽椅子探偵。孤島での殺人事件を推理せよ!…監禁された状態で!?
誘拐されたとある少女。
その誘拐の目的は、少女のいとこの青年に「あるもの」を盗ませるため?
「安楽椅子探偵」、「誘拐事件」、「孤島の館での殺人」、
そして「推理するのは、誘拐されている少女」という、設定の合わせ技が凄い!
なぜこの本を読んだのか
本の雑誌『ダヴィンチ』で、新刊紹介されており、
設定が面白そうだと感じ、読んでみたくなりました。
2.かんたんあらすじ
誘拐された少女・霞。
誘拐犯曰く、霞のいとこ・穂継は、彼女の解放の条件である「あるもの」を手に入れるため、
孤島の館【雷龍楼】へと向かったと語る。
しかし、その館で殺人事件発生!?
そしてなんと、穂継は殺人の容疑者に!?
穂継の疑いを晴らすために協力しろと、誘拐犯に迫られた霞は、
「完全なる密室」の謎解きに挑む。
心に響いたフレーズ
これより油夜島で起きる連続殺人事件の犯人は、外狩詩子ただひとりである。疑り深い読者のため、ここにはなんの叙述トリックも存在しないと付け加えておこう。外狩康弘を殺すのも、上田香と泰造の夫婦を殺すのも、小林健吾を殺すのも、すべて詩子ひとりが計画し実行するという意味であって、それ以外の解釈はない。
本書20P~21P目の見開きによる「読者への挑戦」の結びの文。
いきなり犯人と被害者たちを明らかにしてしまう表現にびっくりしました。
私自身、「疑り深い読者」でしたので、このようにわざわざ書かれていると、
逆に何らかのトリックではないかと疑ってしまい、
これこそ作者のてのひらの上だろうと感じました。
そして「読者への挑戦状」…
この場合の「読者」も、なにかしらの意味が…
にぃには島へ行ってしまった。ということは、ここへ助けには来られない。自分でなんとかするしかない。
霞のモノローグ。
誘拐され、唯一信頼している相手の穂継は、孤島へ向かい助けに来ることはできない状況。
そんな状況が、彼女をある方向へ誘ってしまいます。
極限状態では、思考も極端になりがち。
たとえば、それは、精神疾患「うつの状態」にも似ていると思います。
日頃「死」を身近に感じていなくても、極限状態には、
こんな苦しい状況からは逃れたい、
もう何もしたくない、「死ぬしかない」と、
考えてしまうことは、十分あり得ることです。
だからこそ、誘拐・監禁という極限状態に相手を押し込める犯罪は、
とても悪逆非道なものだと感じました。
「ろくな動機もなしに人を殺す人間はたくさんいるし、明確な動機があっても人を殺さない人間はもっと大勢いる。~犯人は、なんとなく四人を殺したのかもしれないし、周囲の人間には理解できない恨みがあったのかもしれないし、もちろん現実的な損得勘定が働いたのかもしれない。」
鯨井真子のセリフ。
2年前の一酸化炭素中毒死の件で、犯人がいたと仮定した場合の、動機について語る場面のセリフ。
推理小説家・鯨井真子の、動機に対するスタンスが語られています。
動機があるからといって犯人とは限らず、
また動機とは、その人の主観が大きく影響するもの。
だからこそ、動機に対して真剣には捉えていない。
この考え方が、ラスト、犯人の動機を知るタイミングで、再度問われることとなります。
頭では分っていても、心が理解することを拒む、そんなことはあり得ます。
この本を最後まで読んで、動機への価値観が変わりました。
3.まとめ
読んだことで得られたポイント
読み終わった時の後味は、個人的には苦みのあるものでした。
嫌な気分になるミステリーを、「イヤミス」と呼びますが、
この作品を読み終えた際、なんとも言えないため息がこぼれました。
物語としては、サスペンス要素とミステリー要素がいい案配で混じり合い、
とても引き込まれました。
・穂継視点である孤島の館【雷龍楼】パート
・霞視点である監禁状態パート
・推理小説家・鯨井真子と穂継の、2年前の事件を探るパート。
この3つのパートで構成されているため、ラスト、話が収束する感覚は爽快でした。
ただ一方、人間の執着、もしくは業とよばれるものは、とても深く、怖いものだとも感じました。
著者は、2021年第41回横溝正史ミステリ&ホラー大賞〈大賞〉の受賞経験があります。
確かに、この作品のおどろおどろしさも、著者の持ち味なのかもしれないと感じました。
ホラーと言えば、お化けや妖怪変化を想像していましたが、
「結局一番怖いのは人間だ」という作者の意志を感じた気がします。
この本は
・ミステリーを読む際、伏線回収したい人
・イヤミスを読みたい人
・ミステリーに騙されたい人
におすすめな作品です!
この本が気になった方は、是非下記リンクからご確認ください!
↓



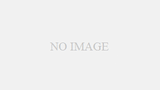
コメント