
こんにちは、てつやまです。
今日紹介する1冊はこちら
『発達障害大全 「脳の個性」について知りたいことすべて』黒坂真由子

本書は、発達障害ついての知りたい人に向けた「あったらよかった1冊」。
発達障害について何らかの知識を得たい人に向けた「わかりやすい解説書」。
人生の選択肢を増やすことができる本。
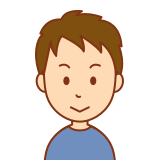
なんでこの本を読んだの?

私自身、広汎性発達障害と診断を受け、発達障害について、
もっと知りたいと感じていました。
複数の視点からみることで、発達障害のことを、より深く知ることができると感じ、読んでみたくなりました。
本の内容で大事な3つのポイント
①発達障害は「脳の個性」
②特性は「重なり」や「濃淡」があるもの
③自分の特性を活かせる環境を見つける
一つずつ解説していきます!
①発達障害は「脳の個性」
発達障害は病気じゃなくて脳の個性!「本人が困難を感じるかどうか」がポイント
本書の中核メッセージは、「発達障害は病気ではなく、脳の個性である」という考え方です。
この視点は、発達障害を持つ人々や彼らと関わる人々の心の負担を大きく軽減してくれます。
著者は、発達障害と病気の定義の違いを明確に示しています。
例えば、糖尿病のような疾患は、本人の自覚症状の有無に関わらず、客観的な数値やデータによって診断されます。
しかし発達障害は違います。
著者によれば、発達障害の特性があっても「本人が困難や障害を感じていない」場合は、
障害とは呼びません。
この考え方は非常に重要です。
つまり、発達障害とはその特性によって
「本人が困難や障害を感じている」ことがポイントなのです。
これこそが発達障害を定義するのが難しい理由のひとつでもあります。
また、発達障害が先天的なものであり、親の教育の結果ではないという医学的事実も強調されています。
これは、発達障害の子を持つ親の罪悪感を減らす上でも大切な視点です。
発達障害はただの少数派!社会の色によって目立ち方が変わる!
著者は、社会的視点からも発達障害を説明しています。
定型発達の人が多数派で、発達障害の特性を持つ人が少数派であるという現実。
そして社会は、多数派の過ごしやすさを優先するもの。
そのため、少数派である発達障害の特性を持つ人が困難さを感じるのは必然とも言えるのです。
私が特に印象に残ったのは、著者の
「発達障害の目立ち方は、多数派の色による」という説明です。
「緑色の自分が、青い世界で生きていればそれほど目立つこともないでしょう。
しかし、赤い世界で生きていれば、とてつもなく目立ってしまいます。
もし、自分と同じ緑色をした世界があれば、自分というものが見分けられなくなるくらい、周りの世界に溶け込んでしまうでしょう」
このようなたとえは、発達障害の本質、「単なる少数派であるだけで、優劣はない」ということを、私たちに知らしめてくれます。
発達障害の困難さは、環境との相互作用で決まる
発達障害の特性を持つ人が感じる困難さは、その特性自体ではなく、
環境との相互作用から生じるものだと言えます。
例えば、短期記憶が保持されにくいという特性があったとしても、
報連相が多方向的に飛び交う職場と、上司・部下の一方向のみの職場では、
前者の方が困難さは大きくなります。
つまり、発達障害による困難さは、環境によって大きく変わるということです。
このように「脳の個性」として発達障害を捉える考え方は、当事者の自己肯定感を高めるだけでなく、周囲の理解も促進します。
もしこの考え方が世間に広まれば、発達障害の人にも、生きやすい世の中になるのではないでしょうか。
発達障害の診断がもたらす「伏線回収」の安心感
本書で印象的だったのは、発達障害の診断が「伏線回収」のような役割を果たすという視点です。
私自身、発達障害の診断を受けたとき、ほっとしたのを覚えています。
「生きづらさにも原因があった」
「自分の努力不足が理由ではなかった」と知ることができたからです。
診断を受ける前は、なぜ周りと違って普通にできないのかわからず、そのわからないこと自体が、ひとつのストレスでした。
推理小説の伏線が回収されると満足感を得られるのと同様に、
発達障害の診断による「伏線回収」は、私に安らぎをもたらしてくれました。
ただし、著者も指摘するように、診断を受けて障害者と判断されて落ち込む人もいるため、一概に喜ばしいこととは言えません。
診断を受けて落ち込んでいる人には「伏線回収して良かったね」などとは言わない方が良いでしょう。
診断によって得られる自己理解は、「自分が何者かわからない」という発達障害の中核的な悩みの解決につながります。
自分の強みと弱みを知り、それに基づいた環境調整や支援を受けることで、より充実した生活を送ることができるようになるのです。
②特性は「重なり」や「濃淡」があるもの
発達障害の特性は「重なり」と「濃淡」があって、人それぞれで異なる
本書の二つ目の重要なポイントは、発達障害の特性には「重なり」と「濃淡」があるという視点です。
発達障害は「ここから発達障害、ここまでは定型発達」というようにはっきり分けられるわけではありません。
ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如・多動症)、LD(学習障害)など様々な分類がありますが、「100%ASD」といった人はめったにいないのです。
例えば、ASDと診断されたものの、時々ADHDの特性により困難さを感じる人もいます。
発達障害には「重なる」部分が多くあります。
さらに、ASDとADHDの重なりがある2人がいたとしても、どちらの特性がより強いかによって、適切なサポートの方法も変わってきます。
このような「濃淡」を自分自身と周囲が認識することが、当事者とサポートする人たちの過ごしやすさに大きく関わるのです。
外に出ず、頭の中がフル回転するタイプの「多動」もある
また、本書には、「ぼーっとしているように見えて、頭のなかでいろいろなことを考えているというタイプの『多動』もある」という指摘もありました。
これは私自身にも強く共感できる部分でした。
子どものころ「ちゃんと聞いているようで実は聞いていないよね」とよく大人に怒られていました。
頭の中ではいろいろなことが巡っていて、人の話が耳に残らない。
それが普通のことだと思っていました。
しかし、このような内的な思考の「多動」も発達障害の特性の一つだと知り、とても腑に落ちました。
決して不真面目でも、相手を蔑ろにしているわけでもない。
脳の特性の一つだと知れて、自分を必要以上に責めなくてもいいと、ほっとしたのです。
このように発達障害の「重なり」と「濃淡」を理解することで、より精密な自己理解と他者理解が可能になります。
特性を理解して立ち位置を決められれば、生きやすくなる!
著者は「自分が何者かわからない」という感覚が、発達障害の核心部分だと述べています。
つまり、逆に考えると、自分の特性を理解して、立ち位置を決められる人は、
発達障害の傾向があってもそれほど困ることはないということです。
「自分が何者かわからない」とは、自分が何が好きで、何が嫌いか、何に心を揺さぶられ、何に耐えられない怒りを覚えるのかなど。
「自分」を語る上で欠かせない要素を、自分自身の特性として理解しているかどうかということです。
私自身、障害者雇用で働き始める際、この「自分の性質を理解する」ことを踏まえて、
「自己取扱説明書」なるものを作成し、就職活動をしました。
企業側にも、「この人はどんな性質があるのか」を分かりやすく伝えられたと思います。
「自分が何が苦手か」を知ることが大事!
特に「自分が何が苦手なのか」を知ることは、非常に重要です。
他の人にとっては些細なことでも、自分にとって苦痛なことならば、自分でできる工夫だけでなく、
働く職場に配慮をお願いすることも必要になるでしょう。
相手の状況や理解の有無は、こちらからどうにかできることではありません。
だからこそ、自分の領分である「自己理解」をしっかり固め、常に考え続けていくことが大切なのです。
このように、発達障害の特性の「重なり」と「濃淡」を理解することは、
自分自身と他者をより深く理解する手助けとなります。
そして、その理解に基づいた適切なサポートや環境調整が、発達障害の特性を持つ人の生きやすさにつながるのです。
「知る」ことから始まる共生
本書全体を通して強調されているのは、「知る」ことの重要性です。
発達障害について知ることは、当事者と周囲の人々の双方にとって、大きなメリットがあります。
著者は「発達障害の人に悪気はない」とわかったとしても、理不尽な言葉を毎日のようにぶつけられれば傷つき、参ってしまうことを認めつつも、
「『そういう人もいる』と『知る』ことから共生が始まり、それが自分の心を守ることにもつながる」と述べています。
発達障害の特性を持つ人と付き合う上で、面倒だと感じる瞬間があることを否定はできません。
しかし、少数派を否定して存続する社会は健全とは言えません。
多かれ少なかれ、互いに付き合う必要がある以上、相手のことを「知る」ことこそ、相互理解の第一歩。
共存共栄を図るためにも、そして一方だけが苦しむという不公平な関係を生み出さないためにも、相互理解は重要です。
また著者は「定型発達というのは、要するに多数派」で、「発達障害者とは、脳の少数派です」と簡潔に表現しています。
生活の中で困りごとが出てくるのは、この社会が多数派である定型発達の人に適した社会だからです。
これは「選挙」の考え方と似ているかもしれません。
基本的に、多数派の意見が強くなりますが、少数派の意見も大事にする取り組みは存在します。
発達障害も、現在は少数派すぎて声が届いていないだけかもしれません。
少数派だとしても、無視できない存在になれば、必ず声は届くはずです。
10年前と比べれば、発達障害についての社会的認知は確実に高まっています。
著者の言葉を借りれば「明日は今日よりも良い日」を信じて、これからも生きていきたいと思います。
③自分の特性を活かせる環境を見つける
自分に合う環境や個人プレーができる仕事を選ぶのが大事
本書の三つ目の重要なポイントは、発達障害の特性を持つ人が、自分に合った環境を見つけることの大切さです。
著者は「ADHDもASDも、個人プレーが向いています。自分1人で取り組める仕事で、結果を出している人は大勢います」と述べています。
発達障害はある意味で個性ですから、それを生かせる仕事を見つけることが大切なのです。
大事なのは、自分の特性を変えようとするのではなく、周りの環境や仕事の職種を変えることです。
個人プレー、1人で取り組める仕事として、在宅で働く仕事やフリーランスとして働くこと、専門性が高く1人でペースを配分できる仕事などが挙げられます。
自分に向く仕事と向かない仕事を知ろう!
また、周囲の理解がある職場選びも重要です。
「あいつはいつも1人で自分勝手にしている」という雰囲気だと、落ち着いて仕事に集中できません。
発達障害の特性を持つ人の雇用体験がある会社だと、少し安心できるでしょう。
一方、「自分に向かない仕事を知ること」も同様に重要です。
何が苦手かがわかれば、その道に進まずに済み、不要なストレスを避けることができます。
つまり、生きづらさも軽減されるのです。
私自身の「自分に向かない仕事」を考えてみると、
- ずっとデスクで過ごす仕事
- 臨機応変さが求められる仕事
- 大きな声が飛び交う職場
- まんべんなく力を発揮することが求められる仕事
- 人間関係が複雑な職場
- ギスギスした空気が漂う職場
- マルチタスクが求められる仕事
- スピードと成果が求められる仕事
- 自分のペースでできない仕事 などが挙げられます。
このように自分の特性を理解した上で、向いている仕事・向いていない仕事を見極めることが、
発達障害の特性を持つ人にとって非常に重要なのです。
発達障害の特性を理解を知ることは、お互いのストレスを軽減させる
また、著者は発達障害の人との関わり方についても言及しています。
特にASDの人は
「感情の安定している人が相手だとわりとうまく付き合える。しかし、感情が不安定な人や威圧的に上から目線でいってくる人とはうまくいかない」
と指摘しています。
これは非常に納得できる点です。
感情が安定している人だと、付き合い方も一定ですが、不安定な人だと、その時々で臨機応変に対応しなければなりません。
臨機応変が苦手なため、うまく対応できず、失敗することになり、それを繰り返すことで苦手意識が積み重なるという悪循環に陥りがちです。
もちろん、定型発達の人も不安定な人や威圧的な人が苦手なことが多いでしょう。
ただ、発達障害の人自体が、すでに社会的なストレスを継続的に受けている状態にあるため、そのダメージをより大きく受けてしまうのかもしれません。
このような特性の理解は、当事者だけでなく周囲の人にとっても重要です。
著者は
「発達障害に対する知識がないと、何度同じことをいってもできない相手に悪意を感じたりすることがあって、それで疲れが増してしまう。善意の人ほど苦しみやすい」
と指摘しています。
発達障害の特性についての知識は、当事者だけではなく周囲の人をも助けるのです。
自分基準で考えると
「あの人わざとやっているんじゃ?」
「嫌われているから?」
と余計なストレスを抱えることになりがちです。
しかし「発達障害の特性として、覚えることが苦手なのだ」という前提があるだけでも、取れる選択肢が広がり、余計なストレスを避けることが可能になります。
まさに「知識は力」なのです。
発達障害とのコミュニケーションは、「違い」を尊重し明確に伝えることが鍵
また、異文化コミュニケーションとの類似性も興味深い視点でした。
著者は
「国籍やバックグラウンドが違う人と働くのと発達障害の人と働くのは、ある意味、似ている」
と述べています。
国籍が異なると、日本人同士なら当たり前に通じることも通じない場合があります。
それは、定型発達の人と発達障害の人の間でも同様です。
どんなに似ていたとしても、他人と全く同じ理解ができるはずもありません。
だからこそ、「違い」を尊重する姿勢が大切なのです。
例えば、著者が紹介している例として、コミュニケーションにおける「ノー」の表現があります。
ある人は「ノー」だと考えている側に「ノーと表現する責任」があると考えていますが、
日本の文化では「空気を読む」ことが重視され、言わずもがなのことをあえて口頭で確認することを「無粋」だとする風潮があります。
日本の「ノーであることを察する責任」という考え方は、特に発達障害の特性を持つ人には難しい場合があります。
上下関係や同調圧力が強い日本では、はっきり「ノー」と答えることに相応の勇気が必要です。
確かに、私もとても断り下手なため、困難さはとてもわかります。
しかし、基本的には、ノーだと考える人には「ノーである」と表現する責任があるのではないでしょうか。
これは発達障害の有無に関わらず、より明確なコミュニケーションのために大切な視点だと感じました。
まとめ
繰り返しとなりますが、本書のポイント
①発達障害は「脳の個性」
②特性は「重なり」や「濃淡」があるもの
③自分の特性を活かせる環境を見つける
『発達障害大全』は、発達障害を「脳の個性」として捉え、その特性の「重なり」と「濃淡」を理解し、自分に合った環境を見つけることの大切さを教えてくれる一冊です。
発達障害の特性は、変えるべきものではなく、理解し活かすべきものです。
それは呼吸のように自然なものであり、変える必要はなく、そして大きく変えることができないものです。
理想的には、呼吸のように自然に生きられる環境が望ましいでしょう。
しかし、そのような環境が整うかどうかは、当事者にとっては制御不可能なことです。
少数派である発達障害の人が感じる苦労と、多数派である定型発達の人が持つ責務。
私は「人間は、どちらの立場にもなり得る」と考えています。
別の場面でなら、現在多数派と思われる人も、少数派になることがあるからです。
だからこそ、どちらの立場にも寄り添える視点を持ちたいと思います。
本書が提案する「発達障害は脳の個性である」という視点は、発達障害の当事者だけでなく、
すべての人にとって価値あるメッセージです。
多様な「脳の個性」を認め合い、互いの違いを尊重する社会。
それは発達障害の人だけでなく、すべての人にとって生きやすい社会なのではないでしょうか。
発達障害についての理解を深め、それを基に行動することは、より思いやりのある優しい社会の構築につながります。
本書はそのための第一歩として、発達障害に関する基本的な知識から実践的なアドバイスまで、幅広い情報を提供してくれます。
私たち一人ひとりが「脳の個性」の多様性を理解し尊重することで、少しずつでも社会は変わっていくはずです。
そして、そのような社会こそが、発達障害の有無に関わらず、すべての人が自分らしく生きられる社会なのだと思います。
この本は
・発達障害の特性を複数の視点から知りたい人
・発達障害の特性における「普遍的なこと」、「異なること」の両方が知りたい人
・発達障害を自分事として考えたい人
におすすめな一冊です!
この本が気になった方は、是非下記リンクからご確認ください!
↓



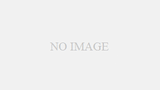
コメント