
こんにちは、てつやまです。
今日紹介する1冊はこちら
『天才肌な発達凸凹っ子の育て方』南雲玲生

本書は、「発達障害の特性を持つ子どもたちと向き合う」大人にとって、
行動や言葉がけのヒントを与えてくれる一冊です。
著者自身の経験をもとに、「共感を大切にした関係づくり」や、
「自立を支える声のかけ方」などが具体的に語られています。
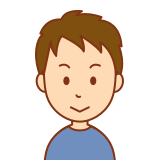
なんでこの本を読んだの?

私自身、広汎性発達障害と診断を受けています。
そのため、発達障害についての関連書籍に興味があり、読んでみたくなりました
本の内容で大事な3つのポイント
①「自分がやりたいからやる」という姿勢が、互いの心を守る
②自分の気持ちや考えを丁寧に言語化する大切さ
③「自分で決めなさい」は、信頼と見守りのメッセージ
一つずつ解説していきます!
①「自分がやりたいからやる」という姿勢が、互いの心を守る
「自分がやりたいからやる」は、お互いのため!
本書『天才肌な発達凸凹っ子の育て方』には、子どもたちと関わるうえでの心構えとして、
「他人のために」ではなく「自分がやりたいからやる」という姿勢が語られています。
この言葉は、一見すると自分のやりたいようにやる、自分勝手な言動に映るかもしれません。
しかし、この考え方は、深い自己理解と謙虚さを伴った態度であり、
「お互いが長く付き合っていくため」の誠実な関係づくりの核心なのです。
善意が不満に変わらない、「本音の選択」の重要性
著者・南雲玲生さんは、自身もADHDの診断を受けた当事者です。
その立場から「自分がやりたいこと」と「他者のためにしていること」の境界を、繊細に捉えてきたのだと感じました。
人は、「善意をもって行動する」とき、いつの間にか「これだけやってあげてるのに」と相手への期待や不満に変化することがあります。
そんなとき、自分が本当に望んで選びとった行動だったかを思い返す視点が、自分自身を守ることにもつながるのです。
「自分がやりたいからやる」が、「自分らしさ」の大事な軸になる!
私自身、広汎性発達障害という診断を受け、自分と他者の境界について考え続けてきました。
相手のことなのに、まるで自分事のように捉えすぎてしまい、他人の領域を侵しすぎてしまうこともありました。
そのなかで、
「押しつけになっていないか」
「相手のためになっているのか」
など、日々迷いながら接してきました。
しかしこの本を読んで、「自分がやりたいからやっている」というシンプルな言葉に救われていると再認識しました。
行動の原点を「相手のため」ではなく「自分がそうしたいから」に置くこと
——それは決して自分勝手ではなく、自分への正直さであり、長く支えるためのバランスの取り方だと思います。
②自分の気持ちや考えを丁寧に言語化する大切さ
「気持ちをちゃんと伝える力」は、とても大事なスキル!
本書では、「自分の気持ちや考えを丁寧に言語化すること」が、
発達障害のある子どもたちだけでなく、私たちすべてにとって大切なスキルであることが繰り返し強調されています。
特に、ADHDやASDの特性をもつ人々は、非言語的なコミュニケーションが苦手である傾向があります。
そのため、「感じたこと」「思ったこと」を言葉にして相手に伝えることが、相互理解の鍵となります。
「うれしい」をちゃんと伝える練習=ソーシャルスキルトレーニング
そのためには、ソーシャルスキルトレーニングのような方法で、伝える技術を磨くことが勧められています。
良い時は率直に「うれしい」「助かる」と伝え、うまくいかないときには「それは困る」「悲しい」と感情に名前をつけて伝えること。
これはすぐにできることではないですが、「言葉で伝える」という意識を持つだけでも大きな一歩になるはずです。
自分の気持ちをちゃんと伝える習慣が、誤解を防ぐカギになる!
印象的だったのは、あるASD傾向の子どもについて「孤立型」というタイプの説明が出てきたことです。
愛着がまったくないわけではないのに、関心を持った対象にしか反応しないため、
「人に無関心」と誤解されやすい性質を持ちます。
この記述に、私自身「話を聞いていない」と咎められる経験を思い出し、深く共感しました。
言語化を習慣にすることで、誤解を防ぎ、必要な距離とつながりの間での調整が可能になります。
単なる情報伝達のためではなく、自分らしさを相手に伝える手段としての言語の大切さを、この本は教えてくれます。
③「自分で決めなさい」は、信頼と見守りのメッセージ
「自分で決めなさい」は、信頼と見守りの優しさがこもった納得感のある言葉
「みんながやっているから、あなたもやりなさい」という言葉に、私は昔から違和感を覚えていました。
それがどれだけ周囲に馴染ませようとしている、善意からくる言葉でも、因果関係として納得がいかなかったからです。
その一方で、この本に出てくる「自分で決めなさい」という言葉は、とても腑に落ちました。
この言葉は、「あなたの判断を尊重する」というあたたかさと、信頼を含んでいます。
単に「放任する」のではなく、「その決断を見守っているよ」という心の距離感こそが、子どもにとっての支えになっていくのだと思います。
「ADHDの子には旅を、ASDの子には愛を」
南雲さんは、「ADHDの子には旅を、ASDの子には愛を」という表現で、それぞれの特性に合った接し方の違いを紹介しています。
そして、「自分で決めなさい」というメッセージが両方に通じる重要な言葉だと述べています。
具体的には、
ADHDの子には、「(信頼を込めて送り出す意味で)自分で決めなさい」。
ASDの子には、「(あなた自身の価値は変わらず、愛される存在だという意味で)自分で決めなさい」。
この場面を読んで、私は、
親に「私の言う通りにしなさい」と叱られていた記憶を思い出しながら、
「自分で決めなさい」という言葉の持つ力強さと、優しさを実感しました。
感情は否定せず、まず共感。どう伝えるかを一緒に考える!
また、感情や考えを否定せず、まず共感し、その上で行動を促す姿勢も本書ではたびたび描かれます。
たとえば、眼鏡を壊された友達をみて、可笑しくて笑ってしまった子どもがいたとき。
「笑っちゃダメ」と怒るのではなく、
「そう思うのは自由。でも、その気持ちをどう表すかが大切だよ」
と伝えることが大事。
しかしこれは、非常に難しい対応です。
しかし、感情そのものに善悪をつけず、行動の選び方を一緒に考えるというのは、大切なアプローチです。
共感からはじまり、自立を支える
——「自分で決めなさい」は、その起点となる言葉でもあるのだと感じました。
まとめ
繰り返しとなりますが、本書のポイント
①「自分がやりたいからやる」という姿勢が、互いの心を守る
②自分の気持ちや考えを丁寧に言語化する大切さ
③「自分で決めなさい」は、信頼と見守りのメッセージ
『天才肌な発達凸凹っ子の育て方』は、発達特性を持つ子どもたちと、どう関わるべきかをテーマにしています。
そしてそれは同時に、すべての人間関係に通じるメッセージでもあると感じました。
自分の気持ちに正直であること
言葉にして伝えること
信頼して見守ること
——これらは、子どもと大人、大人同士の関係においても変わらず大切なことです。
とくに、子育て支援や教育に携わる人はもちろん、自分自身の心のあり方に悩むすべての人にとっても、本書は多くの気づきを与えてくれます。
思いやりや優しさは、感情ではなく、技術である。
南雲さんの言葉の端々には、そんな姿勢が感じられました。
そしてそれは、誰でも少しずつ身につけられるものだという希望にもつながります。
人と人のあいだにある、目には見えない心の橋をどうかけるか
——そのヒントを、私はこの本から受け取りました。今後、誰かと関わる場面で立ち止まったとき、きっとこの本のページを思い出すと思います。
この本は
・発達障害について知りたい人
・子育てに悩む人
・コミュニケーションに苦しんでいる人
におすすめな一冊です!
この本が気になった方は、是非下記リンクからご確認ください!
↓



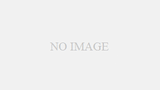
コメント