
こんにちは、てつやまです。
このたび、植松三十里さんの時代小説
『鹿鳴館の花は散らず』を読みました。
《作品情報》
・書名 鹿鳴館の花は散らず
・著者 植松三十里
・出版社 株式会社 PHP研究所
・頁数 271
1.この本のここが凄い!
「鹿鳴館の花」
「日本のナイチンゲール」
と呼ばれた、日本人女性の半生に迫る歴史小説!
「ノブレス・オブリージュ」の人が、困難に立ち向かう!
なぜこの本を読んだのか
「鹿鳴館外交」という言葉は知っていましたが、
どういった時代背景で行われた政策 なのか 深く知ることはなかったので、
気になり読んでみたくなりました。
2.かんたんあらすじ
鍋島榮子(ながこ)は、明治時代に「鹿鳴館の花」と呼ばれた鹿鳴館外交の立役者。
さらに、「日本のナイチンゲール」と呼ばれ、赤十字を立ち上げて戦争や災害で人を助けた行動力の人。
気品と優しさ、そして覚悟を兼ね備えた、混沌の時代を生きた女性の半生を描く歴史小説。
心に響いたフレーズ
「世の中には、あれこれ気にしない無神経さが、大人物であるかのように、勘違いする向きもありますが、殿の旧藩士たちへの細やかな気づかいは、上に立つ方にふさわしい配慮です」
佐野常民が、佐賀藩主・鍋島直大を評したセリフ。
大ざっぱで細かいことも気にしない人物こそ、おおらかで立派な大人物であるかのような風聞。
しかし、上に立つ者こそ、常にこまごましたことへの目配りが大事。
現代における社長業も同じことが言えるのではないかと感じました。
経営という大局的な面を見る必要が迫られる役割ではありますが、だからと言って部下の気持ちをないがしろにしていい理由にはなりません。
「細かいことが気になる癖」を持ちつつ、それに対して結論を出していく。
それが上に立つ者、リーダーの役割なのかもしれません。
病人と家族の間に看護婦が入ることで、双方の負担を減らしたい。そうすれば閉塞的で暗い病室の扉を、開けられるにちがいなかった。榮子は看護婦養成の意義を、改めて自覚した。
榮子自らの体験から得た、家族で病人を看護する中で生まれる葛藤や鬱屈、逼迫した気持ち。
榮子は、そんな人たちの「気持ちがわかる」経験をしてきました。
家族の間や家族と病人の間に第三者が入ることで、閉塞的で暗い空間を開放的にできるのではないか。
そのためには、第三者を育てる看護婦養成の意義がとても重要になってくる、と読者に語り掛けてくる場面。
看病の話だけでなく、そもそも家族間のトラブルは、とてもこじれやすいものです。
そういったトラブルを解決するためにも、第三者の力はとても大事。
自分で何とかしようと考えがちな日本人ですが、他人の知恵を借りることも、人間にできる打開策の一つです。
弱さを見せることは恥ではありません。
弱さを認め、そこから行動を起こすことこそ強さなのだと思いました。
「どんな命令であろうとも、誰からの命令であろうとも、人を殺すのは野蛮だ。人の命を助けるのは尊い。ごく単純な理屈だよ」
佐賀藩主・鍋島直大のセリフ。
確かにその通りだと感じた名セリフ。
どれだけ理由をつけても、人を殺すことは野蛮。人を助けることは尊い。
その原則は、建物の土台のように、決して崩れないものです。
その前提のもとで、人を殺す理由に、どんな事情があったかを考慮する。
それこそが、裁判や司法の役目だと思います。
そして、もし歴史が、その事情をうやむやにして闇に葬ろうとしても、
覚えていてくれる人は必ずいるという、希望の言葉でもあるように受け取りました。
人間はどうしても、目の前のことや煩雑なことに目がくらみ、この原理原則を忘れがちに陥ります。
何か問題や課題にぶつかった時こそ、この前提に立ち返りたいと感じました。
3.まとめ
読んだことで得られたポイント
本作の主人公、鍋島榮子さんは、明治の混沌とした時代を生き抜いた偉人です。
外交の場で「鹿鳴館の花」と呼ばれただけでなく、日本赤十字社の創設に尽力し、
戦争や災害時の支援、障がい児支援、女性教育などにも力を注いだ行動派でした。
外交官の妻として過ごした日々や、夫の看病経験が、その後の社会貢献につながっていたという気づきが、特に心に残りました。
また、「できる方法を考える前に、まず受け入れる決断を」という彼女の言葉には、
今の時代にも通じる、「強さ」と「覚悟」を感じました。
この本を読むと、自分も何かに挑戦したくなる気持ちになるはず!
歴史の中で埋もれがちな人物の輝きを知る喜びも感じられました。
この本は
・歴史好きな人
・波乱万丈な物語が読みたい人
・佐賀県民
におすすめな作品です!
この本が気になった方は、是非下記リンクからご確認ください!
↓



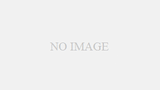
コメント