
こんにちは、てつやまです。
今日紹介する1冊はこちら
『Chat GPT を使い尽くす!深津式プロンプト読本』深津貴之/岩本直久

本書は、著者の深津貴之さんが編み出した「深津式プロンプト」をもとに、
実践的な「Chat GPTのビジネス活用法」を紹介。
プロンプトの工夫ひとつで、資料作成やアイデア出しが驚くほどスムーズに!
「役割」「目的」「出力形式」の3要素を明確に伝えることで、AIの回答精度を飛躍的に高めることができるなど、目から鱗の情報が満載!
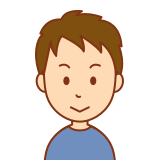
なんでこの本を読んだの?

「ChatGPTには プロンプトが大事」という話は聞いたことがありましたが、具体的にどのようなプロンプトが有効なのかが知りたくて、読んでみました。
本の内容で大事な3つのポイント
①プロンプト(質問)の工夫が成果を左右する
②出力の正しさは自分でチェックすることが大切
③AI時代でもモラルが問われる使い方を心がける
一つずつ解説していきます!
①プロンプト(質問)の工夫が成果を左右する
質問を変えるだけで返ってくる答えが見違える
ChatGPTを触っていて感じるのは、
「質問を変えるだけで返ってくる答えが見違える」という事実です。
本書では、「ChatGPTは確率で続きを書く機械」だと、非常に明快に説明されています。
どれだけ優れた技術であっても、入れるプロンプトの質が低ければ、期待通りの成果は得られません。
ChatGPTに役割を与え、対象読者を指定する
たとえば、「文章を直して」とだけ言えば漠然とした返答になりがちですが、
「38歳男性向けに、親しみやすく、わかりやすくして」
と加えるだけで、精度が格段に変わります。
本書ではさらに、「ChatGPTに役割を与え、対象読者を指定する」ことで精度が増すことも紹介されており、これは人間同士のコミュニケーションと変わらないと感じました。
「最近どう?」と 漠然と聞かれるよりも、
「最近のプライベート、どこか遊びに行った?」と尋ねられた方が、
質問者の意図した 問いの答えは帰ってきやすいものです。
質問の成否すらも訊いてみる
加えて、プロンプトを出す際に
「雑だったら追加情報を求めてください」と指示する方法も印象的でした。
これは、人間側がいかに気をつけて質問をしたとしても、
「聞くべきことを聞けていない」という事態は多々起こりえます。
そこで、あらかじめ
「こちらの質問の仕方が雑だったら、そちらから質問をして」
と相手に頼んでおくのです。
よほど親しい間柄でなければ なかなか言えないことですか、ChatGPT なら嫌な顔もせず 答えてくれます。
ChatGPTとのやりとりでも、双方向の工夫が重要になってくるのだと気づかされました。
②出力の正しさは自分でチェックすることが大切
「出力された答え」は人間が確かめる!
ChatGPTが必ずしも正しい情報を返すとは限らない。
その前提に立って使うことが、この本の重要な教えの一つです。
特に本書では、「ネットや論文を使って、出力をダブルチェックする」という習慣が勧められており、「複数のサイトに当たり、ファクトチェックを行う」プロンプトも紹介されています。
これは、AIがどれだけ便利でも、その出力の正確性は人間が確認しないといけないという姿勢を示しています。
実際、私もChatGPTを使っていて、「それっぽいけれど間違っている」情報に出会うことがあります。
だからこそ、本書が繰り返し述べている
「精度は使い手が担保する」という姿勢は、現代のAI活用者にとって不可欠な視点です。
「AIにできること」と「人ができること」
また、「情報収集はある程度人間が行い、そのデータをChatGPTに処理させる」
というスタイルが紹介されていますが、私もこの考え方に賛成です。
これは、ChatGPTを“思考の補助ツール”として捉え、自分の知識を発展させるために使うという発想です。
例えば、「書籍レビュー作成」などの行為には、この思考が当てはまるのではないかと感じました。
まず、人間の役割として、読書を通じて本のテーマ、印象的な場面、自身の感情的反応などを記録。
そして、AIの役割としては、収集された情報をもとに、読者ターゲットに合わせた要約やレビュー文章を整形・編集。
AIは実際に読書することはできません。
しかし、人間の視点をもとに、構成力や文章整形力という補助的な効力は発揮できるのです。
③AI時代でもモラルが問われる使い方を心がける
使用者側のモラルが大事
AIが身近になった今、忘れてはならないのが「モラル」の話です。
ChatGPTを単なる便利な道具として見るだけでなく、
「何をしてよくて、何が危ないのか」を、
使用する人間側が理解して使うことが求められていると実感しました。
手軽に作品を生み出せる一方で、公表するとなれば、他者の著作権やコンテンツ権に配慮しなくてはいけません。
AIと上手に付き合う
また、誤情報を拡散させないためにも、人間側には、倫理的なフィルターを持って接する義務があると思います。
言語化されていない意図をAIに察してもらうのは難しい。
だからこそ、使う側が意識的に言語化を行い、リスクを認識する姿勢が重要になるのです。
例えば、AIの出力をそのまま鵜呑みにせず、信頼できる外部ソースで情報を再確認する
「情報の二次確認(ファクトチェック)」。
AIの文章に断定的表現があれば、「可能性がある」「一説には」といった表現へ調整する、
「断定表現の調整」など。
全てを依存するのではなく、程よい距離感も大事だと感じました。
まとめ
繰り返しとなりますが、本書のポイント
①プロンプト(質問)の工夫が成果を左右する
②出力の正しさは自分でチェックすることが大切
③AI時代でもモラルが問われる使い方を心がける
『ChatGPTを使い尽くす!深津式プロンプト読本』は、プロンプトの具体例列挙だけでなく、ChatGPTを使いこなすために必要な“思考のクセ”を教えてくれる一冊だと感じました。
プロンプトの工夫は、AIから得られる成果を大きく左右します。
出力された情報の精度は、最終的には人間が見極める必要があります。
そして、AIを使う上では、社会的な責任とモラルも問われます。
これらすべてが一体となったとき、ようやくAIとの“健全な付き合い方”が見えてくるのだと学びました。
この本は
・AIとの距離感に悩んでる人
・うまく質問できないと感じている人
・便利すぎるツールにちょっと不安を感じてる人
におすすめな一冊です!
この本が気になった方は、是非下記リンクからご確認ください!
↓


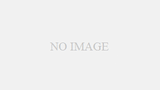

コメント